頂きましたの意味と使い方|いただきました・戴きましたとの使い分けも
頂きましたの意味・使い方はご存知ですか?この記事では平仮名のいただきましたや常用漢字ではない戴きましたとの使い分けや敬語表現などについてお伝えしています。美味しくいただきました・教えてもらいましたなどの意味を表すことができる頂きましたを適切に使えるようにお役立てください。
※商品PRを含む記事です。当メディアはAmazonアソシエイト、楽天アフィリエイトを始めとした各種アフィリエイトプログラムに参加しています。当サービスの記事で紹介している商品を購入すると、売上の一部が弊社に還元されます。
目次
頂きましたの意味と類語と英語は?
頂きましたの意味は飲食する・もらう

頂きましたの意味は飲食する・もらうという意味です。頂きましたという表現は飲食する・もらうという意味の謙譲語表現です。謙譲語表現とは、自分の立場を下げることによって相手に敬意を表すための言葉遣いです。
頂きましたという謙譲語表現を使った例としては「昨日は先輩の自宅で夕食を頂きました」などの表現がされます。「昨日は先輩の自宅で夕食を頂きました」と言う場合の「頂きました」には「飲食をさせてもらいました」という意味合いが込められます。
「頂きました」という言葉をもらうという謙譲語表現で使う場合には、「お客様からお礼の言葉を頂きました」という表現で言い表すことができます。この場合も「頂きました」という謙譲語表現を使うことによって自分の立場を下げ、お客様を立てることができます。そうすることでお客様に敬意を表すことができます。
頂きましたの類語は「頂戴した」

頂きましたの類語は「頂戴した」です。頂戴したという言葉には、相手からもらったものを非常に丁寧に扱うといった意味合いが込められています。例えば「お礼の品を頂戴しました」といった表現をすることで、相手を丁重に扱い敬意を表すニュアンスを含めることができます。
頂戴という言葉には「飲食する」「もらう」「~をしてほしい」「頭の上に掲げて持つ」などといった意味合いがあります。頂戴の「頂」という字は「頂点」などという言葉にも使われるように、一番高い所を意味します。また「戴」という言葉には「上に掲げ持つ」「頭に載せる」といった意味合いがあります。
これらの言葉がくっついた「頂戴」という言葉には、相手からいただいた物などを丁重で謙虚な気持ちで取り扱うといったニュアンスが含まれます。ちなみに頂戴という言葉の意味については以下のサイトで詳しく説明されていましたので、参考になさってください。
頂戴(チョウダイ)とは頂きましたを「頂戴いたしました」という敬語にすると二重敬語になる

頂きましたを「頂戴いたしました」という敬語にすると二重敬語になるため注意が必要です。二重敬語とは、1つの文章の中に同じ種類の敬語を2種類以上用いることを言います。二重敬語は間違った敬語表現であることから、言葉遣いに厳しい人の中には不快に感じる人も少なくないと言われていますので注意が必要です。
頂戴いたしましたの「頂戴」は謙譲語表現であり、「いたしました」という表現も謙譲語表現です。そのため頂戴いたしましたという表現は二重敬語であり、間違った敬語表現であると言えます。他にも二重敬語には「仰られる(おっしゃられる)」「ご参上する」「おいでになられました」などの言葉遣いが挙げられます。
しかし二重敬語であっても、日常的に多くの人が使う二重敬語は許容される傾向があります。例えば「お伺いする」「お召し上がりになる」「ご案内申し上げる」などです。二重敬語については以下のサイトで詳しく紹介されていたので、ぜひ参考になさってください。
よくある二重敬語の例文と正しい敬語の例文頂きましたの英語「彼からあなたの連絡先を教えてもらいました」

頂きましたの英語は「彼からあなたの連絡先を教えてもらいました」という意味の「He gave me your ○○」です。gaveはあげたという過去形の表現であることから、教えていただいたという意味になります。○○にphone number・email addressなどを当てはめることで使えます。
ビジネスにおいては横のつながりが大切であると言われていることから、人間関係を大切にする人の中には積極的に手助けしてくれそうな人を紹介してくれることがあります。「自分では力になれないけれど、この分野に詳しい知人がいる。この人に連絡してみて」などと言って快く知人を紹介してくれる人ですね。
このように困っている人を見て何らかの役に立ちたいという親切心によって、知人の連絡先などを教えてくれるケースに「He gave me your ○○」という表現が使えます。以下のサイトでは知人から連絡先を頂きましたという英語表現が紹介されていたのでご覧ください。
「山岡さんからご連絡先を頂きました」 英語の営業でどう言う?頂きましたの使い方例文3選!
頂きましたの使い方例文①美味しく頂きました

頂きましたの使い方例文の1番目は、美味しく頂きましたという使い方です。美味しく頂きましたという言い回しで使われる「いただきました」という表現には「美味しく食べた」「美味しく食べさせてもらった」といった意味合いがあります。
相手から食事をご馳走してもらった際などに、相手に対する敬意を表現するために美味しくいただきましたという謙譲語表現を用います。このように自分の立場をへりくだらせる謙譲語表現を使うことで結果的に相手を高め、丁重で謙虚な姿勢を表すことができます。
美味しく頂きましたという表現を使う場合には、単に相手から食べ物や飲み物を美味しくいただいたという意味合いだけではなく、相手に対してありがたい気持ちを抱いているという感謝の意を表現することにもつながります。もう少し硬い表現には頂戴しましたという言葉を使うことができます。
頂きましたの使い方例文②先方からは既に了承を頂きました

頂きましたの使い方例文の2番目は、先方からは既に了承を頂きましたという使い方です。ビジネスシーンでは相手に先に話を通してから物事を進める方が円滑な仕事ができるケースは珍しくありません。相手に許可を得たり連絡をしないまま勝手に仕事を進めると、相手に対して失礼にあたるからです。
何の連絡もなしに仕事を進めてしまうと、仕事の主導権が自分の側にあるという態度を暗に示すことになってしまいます。こういった姿勢は相手よりも自分の方が上の立場にあるといった意味合いにとられかねません。このようなことから、ビジネスシーンにおいては関係者に細かく情報共有することが大切であると言われています。
逆に、周りの関係者に細かく情報を共有したり、丁寧に連絡をする姿勢を示しておけば好感を抱かれやすく、しいては円滑に仕事を進めやすいと言われています。ちなみに最近のビジネスシーンでは情報を共有するという意味合いでシェアという言葉が使われることが多くなったので以下の記事も合わせてご覧ください。
頂きましたの使い方例文③正しい漢字表記を教えて頂きました

頂きましたの使い方例文の3番目は、正しい漢字表記を教えて頂きましたという使い方です。ビジネスシーンでは相手の漢字表記を間違えてしまうことは非常に失礼なこととされています。日本語には同じ読みをするにも関わらず異なる漢字表記となるものがあります。
他にも会社名などに使われる漢字に特別な意味合いを込めて、通常の漢字とは異なる漢字表記を用いる会社もあります。このようなことから正式な文書を提出する前には取引先の担当者の名前や責任者の名前などを事前に確認しておくことが必要です。
こういった問題は考えてもわからないので、結局のところは相手に丁重に質問をするしかないと言われています。相手がとっつきにくい人であったり、難しい性格をしている際には漢字表記を聞きにくいことがあります。そのため本人に聞くのではなく周囲の人に質問するといった配慮をするビジネスパーソンも珍しくありません。
いただきましたの意味と使い方|頂きましたとの違いや使い分けは?
いただきましたの意味と使い方①頂きましたとの違いは補助動詞かどうか

いただきましたの意味と使い方の1番目である、頂きましたとの違いは補助動詞かどうかです。いただきましたは補助動詞であり、頂きましたは補助動詞ではありません。補助動詞とは、その言葉のもともとの意味ではなく、くっつく言葉の意味に補助的な意味を付け足す働きをする動詞のことです。
例えば「彼はアメリカ人である」という表現に使われる「ある」という言葉は「ある」「存在する」という言葉の意味ではなく、アメリカ人という言葉にくっついて「~です」といった意味合いで使われる補助動詞です。
他にも「雨が降っている」という表現の「いる」という言葉ももともとの意味で使われていない補助動詞です。この場合の「いる」は、何かの存在を表す「いる」ではなく、雨が降る状況を表現するための補助的な意味合いとして使われています。ちなみに補助動詞については以下のサイトに詳しく説明されていたのでご覧ください。
補助動詞(ホジョドウシ)とはいただきましたの意味と使い方②頂きましたとの使い分けは動詞につくか
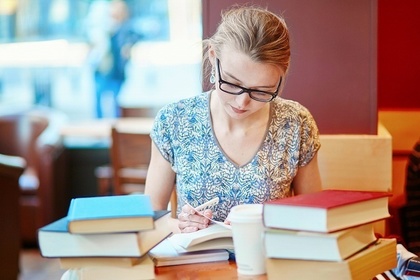
いただきましたの意味と使い方の2番目である頂きましたとの使い分けは動詞につくかどうかです。いただきましたは補助動詞なので、動詞を補助するために動詞にくっつきます。その一方で頂きましたは謙譲語の「飲食する」「もらう」という動詞であることから、他の動詞にくっつくことはありません。
いただきましたと表記する場合には「お忙しい中お越しいただきまして誠にありがとうございます」などといった表現がされます。この場合、いただきましたという言葉は「お越しになる」という動詞にくっついた表現になります。
このような働きをする補助動詞は文部科学省の定めにより平仮名で書くこととされていることから「お忙しい中お越しいただきまして誠にありがとうございます」と書くことが正しいと言われています。しかし「お忙しい中お越し頂きまして」と書かれるケースも少なくないことから許容されることも少なくありません。
戴きましたの意味と使い方|頂きましたとの違いや使い分けは?
戴きましたの意味と使い方①頂きましたとの違いは常用漢字かどうか

戴きましたの意味と使い方の1番目である頂きましたとの違いは常用漢字かどうかという違いです。戴きましたという表現は常用漢字ではありませんが、頂きましたは常用漢字です。戴きましたは常用漢字ではないことから、頻繁に使われることは少ないと言われています。
常用漢字とは1981年に内閣の告示によって示された漢字です。戦後に定められた当用漢字は戦後の時代に定められたものであり、「今後、漢字を廃止していこう」というGHQの考え方が色濃く反映された厳しいルールでした。そのため当用漢字以外の漢字を使うことは許されていませんでした。
しかしその後に示された常用漢字は一般的に使われる漢字として示されたものに過ぎないことから、常用外の漢字を使うことも認められています。常用漢字・当用漢字については以下のサイトで詳しく紹介されていましたので参考になさってください。
常用漢字と当用漢字の違い戴きましたの意味と使い方②頂きましたとの使い分けは頂いた物による

戴きましたの意味と使い方の2番目である頂きましたとの使い分けは頂いた物によるというものです。戴きましたという表現はお礼の品などの品物をもらった時に使われるケースが多いと言われています。
戴くという言葉には「上に掲げ持つ」「頭に載せる」といった意味合いがあることから、相手に対して大きな敬意を表したうえで品物などを受け取るといった意味が込められます。また戴くという表記が常用漢字ではないため、通常の物をいただいた時よりも重大で深い意味合いを込めたい時に使われることが多いと言われています。
その一方で頂きましたという表現には、戴きましたというニュアンスに含まれるほどの大きな意味合いが含まれないと言われています。戴きましたと戴きましたにはこのような違いがあるため、いただいた物によって言葉に込めるニュアンスが異なるという使い分けがされます。
頂きましたを把握して正しく使いこなしましょう
頂きましたという表現は平仮名でいただきましたと書く場合もあれば、戴きましたというように常用外の漢字を使うケースがあります。これらの表現の意味を理解することで正しい使い分けができます。ビジネスシーンにおいてはしっかりとした言葉の使い方、使い分けができる人は周囲の人から信頼されやすいと言われています。
そのため、正しい言葉遣いを把握して正しくつかいこなしましょう。最後に頂きましたのようにビジネスシーンで使える表現についてお伝えしている記事を紹介します。
「これまでの経験を仕事にいかしたい」などといった表現をする際の「いかす」という漢字表記についてお伝えした記事です。こういった漢字表記に自信が持てると、仕事における言動にも自信が現れると言われているので役立ててください。
商品やサービスを紹介する記事の内容は、必ずしもそれらの効能・効果を保証するものではございません。
商品やサービスのご購入・ご利用に関して、当メディア運営者は一切の責任を負いません。
![chokotty[ちょこってぃ]](https://cktt.jp/assets/common/cktt_logo_PC_2-40c5a35e8da64f225f3dcdf1b548a3f3373f85eeab336668a1c00fe9a8ab42c8.png)











