「ありき(有りき)」の意味と類語とは?仮定/前提/言い含める
「ありき」の意味をご存知ですか?漢字では「有りき」と書くこの言葉は、類語として仮定・前提・言い含める・念頭などがあります。この記事では意味と例文、使い方などを紹介していきます。誤用されやすい「ありき」を正しく覚えましょう。
※商品PRを含む記事です。当メディアはAmazonアソシエイト、楽天アフィリエイトを始めとした各種アフィリエイトプログラムに参加しています。当サービスの記事で紹介している商品を購入すると、売上の一部が弊社に還元されます。
目次
「ありき」とは?漢字や意味は?
「ありき」は「有りき」と書く
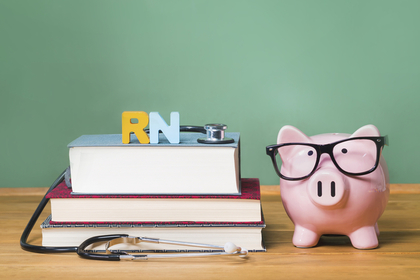
「ありき」は「有りき」と書きます。また「在りき」とも書きます。「有る」と「在る」は、どちらも同じ意味ですので、「有りき」と「在りき」の漢字の違いによる意味の変化はありません。しかし漢字の「有りき」や「在りき」は、古語として使われることが多く、現代語としてはひらがな表記の「ありき」が主流です。
「ありき」とは①「あるという前提として」や「仮定して」という意味

「ありき」とは「あるということを前提として」や「あると仮定して」という意味です。「ありき」は存在を表す「ある」に「き」をつけた言葉です。
「き」はもともと、思い起こすことを表す助動詞でしたが、平安のころにはすでに使い方が分からなくなっていて完了と存続を表す言葉になりました。現代でも主に完了と継続を表す言葉として用います。
つまり「ありき」とは「有る」ことが完了し存続している状態で「過去に存在した、そして現在も存在しているもの」ということです。
「ありき」とは②「言い含める」や「念頭に置く」という意味

「ありき」には言い含める意味や、念頭に置いて考えるなどの意味もあります。例えば「認めないという結果ありきで話をしてください」とあれば「認められないので言い含めておいてください」という意味になります。また「安全ありきで行動する」という言葉は「安全を念頭に置いて行動する」という意味になります。
「ありき」とは③「あった」の古語

「ありき」とは「あった」の古語です。古典で「ありき」を使った文章が出てきたら「あった」と現代語訳します。また古典では「歩き回る」という意味で「ありき」を使うことがあります。「歩き回る」という意味の「ありき」を覚えておくと、古典を読み解く際に混乱せずに読み解くことができます。
「ありき」同様、日常やビジネスシーンでも多用されながらも誤用されやすい「いずれ」と「いづれ」の違いについての、詳しい記事がこちらにありますので、あわせてご覧ください。
「ありき(有りき)」の使い方!例文5選!
「ありき(有りき)」の使い方!例文①結論ありき

「ありき(有りき)」使い方の例文1つ目は「結論ありき」です。「結論ありきで話が進む」などと使われます。これは、結論が決まった状態で、その結論に向かって議論がなされている様子を表した言葉で、ニュースや新聞など政治関連の報道でよく耳にします。
「結論ありきの議会には意味がない」や「結論ありきの話し合いだったので時間の無駄だ」などネガティブな表現として使われることが多い言葉です。
「ありき(有りき)」の使い方!例文②○○ありきで考える

「ありき(有りき)」の使い方2つ目は「○○ありきで考える」です。これは「ありき」の直前につく言葉が「前提としてあると考える」という意味です。使い方としては「子供のやることは、失敗ありきで考える」や「この商品開発は若者の需要ありきで考える」などです。
この「ありき」の用法は、完了している事柄に使われてはおらず「完了しているものととらえて」という推定の意味で使われています。ですので、本来の「ありき」の使い方から鑑みると、誤用ということになります。ですが今では広く浸透している使い方なので、現在では誤用ではないとみなされています。
「ありき(有りき)」の使い方!例文③お客様ありき

「ありき(有りき)」の使い方例文3つ目は「お客様ありき」です。これは「お客様があってこそ」という理念を念頭に行動するという意味があります。例文としては「当店では、お客様ありきで接客応対しております」などがあります。
類似の使い方としては「この人ありき」や「支持者ありき」などがあります。これは特定の他者があってこその自分だという感謝を表した言葉です。
しかし「夫ありきの生活」や「両親ありきの自分」といった身内と「ありき」を合わせた言葉になると「その特定の他者がなくては生きていけない」という依存の意味を持ち合わせます。
「ありき(有りき)」の使い方!例文④審議ありき

「ありき(有りき)」の使い方4つ目は「審議ありき」です。これは例文1つ目の「結論ありき」とは反対の意味を持ちます。例文としては「結論は審議ありきで導き出すべきだ」や「この問題は審議ありきの課題である」などです。意味は「問題を解決するための審議を経過してやっと、結果や結論が導かれる」という意味です。
「結論ありき」を文章で使う場合は「結論ありきの判決」などというように、結果としてそうであったというような場合に使われます。ですが「審議ありき」は「この話は審議ありきで進めてもらいたい」など、希望を込めた使われ方がされます。
「ありき(有りき)」の使い方!例文⑤かくありき

「ありき(有りき)」の使い方5つ目は「かくありき」です。「かく」とは「こう」「このように」「こんなふうに」の古語です。そして「ありき」は「あった」の古語ですので、つまり「かくありき」とは「こうあった」「こうであった」「このようであった」などの意味を持ちます。
例文としては「かつて青春はかくありき(かつて青春はこうであった)」や「指導者はかくありき(指導者はこのようであった)」などです。「かくありき」は「こうであるべき」と現代語訳されやすい言葉ですが、これは誤訳です。
「こうであるべき」を古語に変換すると「かくあるべし」です。例文としては「武士たるもの、かくあるべし」で、意味としては「武士というのは、こうであるべきだ」です。「かくありき」と「かくあるべし」は間違えやすいので、しっかりと覚えておきましょう。
「ありき(有りき)」の類語と使い方例文!
「ありき」の類語と使い方例文①仮定

「ありき」の類語と使い方の例文の1つ目は「仮定」です。仮定とは、不確かな物事を仮にあると定めることです。「仮定」の例文は「そのうわさが、事実だと仮定するとして」や「ここに円があると仮定して」などです。
「仮定」は「○○ありきで考える」という文章の置き換えとして使えます。例文としては「臨時収入ありきで考える」という言葉を「臨時収入があると仮定して考える」と置き換えます。
今は、よく使われるようになった用法の「○○ありきで考える」は、本来の使い方としては誤用ですので「仮定」を置き換えて使う方が無難です。
「ありき」の類語と使い方の例文②前提

「ありき」の類語と使い方例文の2つ目は「前提」です。前提とは、あることが成り立つための、前置きとしての条件のことです。使い方の例文は「結婚を前提に、お付き合いする」や「前提で、はじかれる」があります。
「ありき」を「前提」に置き換える例文として「これは読者ありきの小説です」を「これは読者が喜んでくださることを前提に書かれた小説です」と置き換えます。「ありき」より「前提」の方が他者の判断や反応にゆだねる意味合いが強くなります。
「ありき」の類語と使い方例文③言い含める

「ありき」の類語と使い方例文3つ目は「言い含める」です。言い含めるとは、物事をあらかじめに言っておき、承知させることです。または分かりやすいように説明することです。例文は「子供に言い含める」「必ずやるように、言い含める」などです。
「ありき」には「○○ありきで話を進める」など「事実がこうだから何と言おうと認めてもらう」といった、相手を突き放した感じを与えます。ですが「言い含める」には「事実はこうだが、納得できないようなら相手が納得できるまで説明する」という丁寧さも含まれます。
「ありき」と「言い含める」の置き換え例としては「この商品開発は男性の需要ありきであることを伝えてください」を「この商品は男性がターゲットであることを言い含めて開発してください」と置き換えます。「言い含める」は「ありき」と比べて相手が自分より弱い立場の時に使われます。
「ありき」の類語と使い方例文④念頭に置く

「ありき(有りき)」の類語と使い方例文4つ目は「念頭に置く」です。「念頭」の意味は考えが、頭の中にある様子のことを言います。「念頭に置く」という慣用句になると、常に心にとどめておくこと。または、忘れないように心がけることという意味になります。
反対の意味を持つ「念頭」の使い方に「念頭にない」があります。これは、最初からそのような考えがないことを意味します。よく使われる「念頭に入れて」は「考えに入れて」と混同された誤用です。間違えやすいので注意しましょう。
念頭に置くの例文は「安全を念頭に置いて運転する」です。「ありき」と「念頭に置く」の置き換えの例として「海外のマーケットありきで商品開発をする」を「海外のマーケットを念頭に置き商品開発する」になります。「ありき」より「念頭に置く」のほうが、強制の意味合いが薄くなります。
「ありき(有りき)」の誤用
不確定なことに「ありき(有りき)」を使うのは誤用

不確定なことに「ありき」を使うのは誤用です。予定や方針、希望などの完了していない不確定な事柄を伝えるために、使われることがありますがこの使われ方は間違いです。例をあげると「予算は今後の売り上げありきで決定します」などです。
「今後の売り上げ」とは、確定していないことです。つまり完了していないことですので「ありき」を使うのは誤りです。ビジネスの場ではこういった予想に「ありき」を使うシーンが見受けられますが、正しい用法を知っているものからすると違和感がある使い方ですので、気をつけてください。
本来は「はじめに○○ありき」でないと誤用

本来は「はじめに○○ありき」でないと誤用です。なぜなら古語の「ありき」と現代語の「ありき」では使い方が違うからです。古語の場合は日常的なありふれた言い方でしたが、現代語のありきは限定的な使い方をしています。これは聖書の「はじめに言葉ありき」をもじった言い方だからです。
「はじめに言葉ありき」をもじった言い方である以上は「はじめに」と「ありき」は、切り離してはいけないのです。ですので現在の使い方の完了と継続の助動詞としての「ありき」は、由来をたどれば誤用ということになります.
ですが「本来は」と前置きしたのは、長らく間違った使われ方をしていたので、今では「はじめに」をつけない助動詞としての使い方も誤用ではないとされているからです。
「ありき」に似た言葉
「ありき」に似た言葉①ありきたり

「ありき」に似た言葉の1つ目に「ありきたり」があります。意味は、全く珍しくないこと。ありふれたさまです。「ありきたり」の「あり」は「ありき」の「あり」と同じで「有り(在り)」と漢字表記し、そこにあること、存在することを意味します。
「きたり」は「来たり」と書きます。これは「来たる」が「有り」とくっついたことで「有り来たり」の形容詞として、用いられた語です。「来たる」は、現在に至るまでし続けることを意味します。例文としては「ありきたりの話」などです。
「ありき」に似た言葉②ありけり

「ありき」に似た言葉の2つ目は「ありけり」があります。こちらも「あり」は漢字では「有り(在り)」と書きます。「けり」は助動詞で、~だった。だそうだ。だということだ。などの意味を持ち、過去の事柄の伝聞として使われます。「ありけり」の意味は、あったそうだ。いたそうだ。などです。
ありけりは、古語ですので現代では使われません。「ありけり」の有名な用法として竹取物語の今は昔から始まる「竹取の翁という者、ありけり」です。古典ではよく使われる言葉ですので、ぜひ覚えておきましょう。
誤用されやすい「ありき」は類語と一緒に覚えよう
古語として使われる場合と、現代語としての使われ方でも全く異なる「ありき」は、今なお誤用されやすい言葉です。ですが、日常や仕事の場でもよく使う言葉ですので、使い方を正しく知っておくことが大事です。
また、類語をいくつか知識に加えておくと「ありき」の使い方に自信がないときや、文脈を正しく相手に伝えたいときなどに置き換えの言葉として使えます。変化していく言葉の意味を正しく読み取って、臨機応変に対処していきましょう。
商品やサービスを紹介する記事の内容は、必ずしもそれらの効能・効果を保証するものではございません。
商品やサービスのご購入・ご利用に関して、当メディア運営者は一切の責任を負いません。
![chokotty[ちょこってぃ]](https://cktt.jp/assets/common/cktt_logo_PC_2-40c5a35e8da64f225f3dcdf1b548a3f3373f85eeab336668a1c00fe9a8ab42c8.png)










