軋轢の読み方と使い方は?確執との意味の違いと言葉の語源・類語も
「軋轢」という言葉をご存知ですか?ここでは「軋轢」の言葉の読み方や語源、「軋轢を生む」などの例文の使い方について丁寧に解説しています。「軋轢」の英語での表現や、類語である「確執」との意味の違いについてもご紹介していますので、興味のある方はぜひご覧ください!
※商品PRを含む記事です。当メディアはAmazonアソシエイト、楽天アフィリエイトを始めとした各種アフィリエイトプログラムに参加しています。当サービスの記事で紹介している商品を購入すると、売上の一部が弊社に還元されます。
目次
軋轢の漢字の読み方・意味は?
「軋轢」の読み方と構成している漢字の読み方

「軋轢」の読み方は「あつれき」です。「軋轢」を構成する「軋」は、訓読みでは「きし(む)」「きし(る)」という読み方になり、音読みでは「アツ」という読み方になります。「軋轢」の「轢」は、訓読みでは「きし(む・る)」という読み方になり、音読みでは「リャク」「レキ」という読み方をします。
「軋轢」の品詞
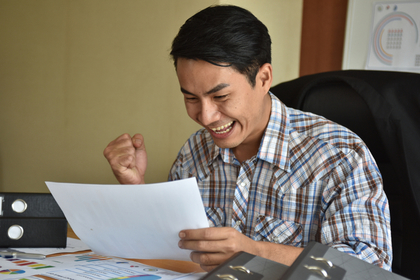
「軋轢」の品詞は名詞です。なので「軋轢する」という使い方は絶対にしません。逆に類語である「確執」は名詞だけではなく動詞としても使いますので、「確執する」という使い方もできます。
「軋轢」の意味とは「仲が悪くなること」

「軋轢」の意味は、「争い」「仲たがい」「葛藤」「調和しない状態」「不和」「人の意見や行動、性格が衝突すること」という言意味があります。つまり「軋轢」の意味とは不和になっている状態を指し、「仲が悪くなること」という意味なのです。
軋轢の正しい使い方と用例
「軋轢」の正しい使い方と用例①軋轢を生む

「軋轢」の正しい使い方と用例の1つ目は「軋轢を生む」です。関係性に不和な状態が起こることを「軋轢を生む」といいますが、「軋轢を作る」とは言いません。例文は「恋愛は場合によっては友達同士の人間関係に軋轢を生むこともあります」になります。
「軋轢」の正しい使い方と用例②軋轢を避ける

「軋轢」の正しい使い方と用例の2つ目は「軋轢を避ける」です。「軋轢を避ける」とは不和や不仲な状態を回避することです。例文は、「職員との軋轢を避けるためにも、上層部と一般職員との話し合いが重要です」になります。
「軋轢」の正しい使い方と用例③軋轢がある

「軋轢」の正しい使い方と用例の3つ目は「軋轢がある」です。関係性において、すでに確執や不和がある場合に「軋轢がある」という表現を使います。「あのバンドグループの活動休止の真相は、メンバー間に軋轢があったようだと、まことしやかにファンの間でささやかれていました」が例文になります。
「軋轢」の正しい使い方と用例④軋轢を生じる

「軋轢」の正しい使い方と用例の4つ目は「軋轢を生じる(しょうじる)」です。「軋轢を生じる」は「軋轢を生む」と意味も用法も同じですが「軋轢を生む」よりも堅苦しい言葉のニュアンスがあります。例文は「この学校のテニス部は優秀だが、厳しい練習のせいか1学年上の先輩と後輩の間に軋轢を生じる伝統がある」です。
軋轢と確執の言葉の意味に違いはあるの?
「確執」の読み方と意味

「確執」という言葉は、いくつかある「軋轢」の類語の1つです。「確執」は「かくしつ」と読みます。「確執」は「お互いの意見を強く主張し、決して相手に譲らないこと」「自分の主張を譲らないことが理由となって起こる不和のこと」という意味があります。
「確執」という言葉の語源は漢語から

「確執」という言葉の語源は漢語からきています。漢語での「確執」の意味は「はっきりと(確)物事をとりおこなう(執)」です。日本語として使われるまでは、「お互いの意見が対立する」という意味はありませんでした。
「軋轢」と「確執」の意味の違い

「軋轢」とは関係が悪くなることや不和の状態全般を指します。一方で「確執」とはお互いの意見が対立することで起こる不和のことを指します。「軋轢」と「確執」の意味の違いをもう少しクリアにすると、「軋轢」が起こる要因の1つが「確執」であると考えると理解しやすいです。
軋轢の類語は?
軋轢の類語①行き違い
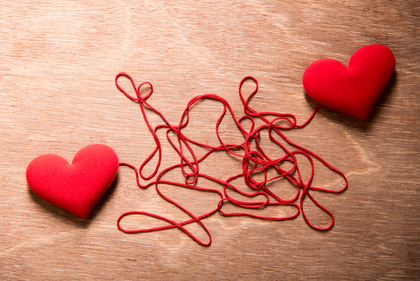
「軋轢」の類語の1つ目は「行き違い」です。「行き違い」は「すれ違いが起こることで、出会えなくなること」とか、「 意志がうまく通じず、誤解やくい違いが起こること」という意味です。例文は、「あの2人は大学進学後行き違いが多くなったせいで、別れることになったそうだ」になります。
軋轢の類語②紛争

「軋轢」の類語の2つ目は「紛争」です。「紛争」とは「ふんそう」と読みます。1970年代に盛んだったものに「大学紛争」というものがあります。「紛争」は「もめごと」や「事態がもつれて争うこと」という意味があります。例文は「隣り合った国同士というものは、領土問題で紛争を起こすことが多い」です。
軋轢の類語③反目

「軋轢」の類語の3つ目は「反目」です。「反目」は「はんもく」と読みます。例文は、「あの2人は小学生の時から仲が悪く、グループ同士も反目しあっていた」とか、「私の家と夫の家は互いに同じ場所の出身ですが、反目しあっている家の出であったので、結婚するのが大変でした」になります。
軋轢の類語④不和

「軋轢」の類語の4つ目は「不和」です。「不和」の意味は「人間関係において仲が悪いこと」です。「両親の不和が原因で、彼女は男性不信に陥っている」とか、「姑と母の中が不和なのは、世間一般でよくあることです」が例文になります。
軋轢の類語⑤不協和音

「軋轢」の類語の5つ目は「不協和音」です。もともとは音楽の協和音の反対語で、「同時に響く2つ以上の音が、協和しない状態にある和音」のことを指す言葉ですがそこから「調和しない人間関係のたとえ」の意味を持ちます。「彼らの結婚生活は、初めから不協和音の兆候があった」が例文になります。
軋轢の類語⑥摩擦

「軋轢」の類語の6つ目は「摩擦」です。「摩擦」のもともとの意味は「2つ以上の物体がこすりあわされること」ですが、そこから「人間関係において、意見や感情の食い違いが起こることによって、仲が悪くなること」という意味があります。例文は「この会社では、若手が人間関係の摩擦で仕事を辞める人が多い」になります。
軋轢の類語⑦不仲

「軋轢」の類語の7つ目は「不仲」です。「不仲」の意味は文字通り「仲の良くないこと」で、人間関係においてネガティブな関係を表現します。例文は、「あの2人の不仲は社内では有名だ」「あの人が再婚しないのは、最初の結婚での嫁と姑の不仲が離婚の原因と言われているらしい」になります。
軋轢の類語⑧齟齬

「軋轢」の類語の8つ目は「齟齬」です。「軋轢」と同様に難しい漢字の「齟齬」の読み方は「そご」です。「齟齬」の意味は人間関係において、「気性や性格がかみ合わなく、食い違うこと」という意味で使われます。「決定的なことが起こって、両者の関係に齟齬が生じた」「夫婦関係に齟齬をきたした」が例文になります。
また、下記の関連記事では「齟齬」についてのい英語や使い方なども詳しく紹介されていますので、気になる方は合わせてご覧ください。
軋轢の類語⑨対立

「軋轢」の類語の9つ目は「対立」です。「対立」の意味は「反対の立場に立って2人のひとや2つのものの集団が張り合うこと」です。「営業1課と営業2課の対立は、もともとは部長同士の対立からきている」「歴史的に見ても、欧米でもアジアでも、隣国同士というものは協調するよりも対立しやすい」が例文になります。
軋轢を英語で言うと何になる?
「軋轢」の英語表現①friction

「軋轢」の英語表現の1つ目は「friction」です。「friction」の意味は「軋轢」「不和」「(意見の)衝突」「摩擦」です。例文は、「The friction between them has become more obvious.(彼らの間にある軋轢が露骨になってきました)」です。
「軋轢」の英語表現②dissension

「軋轢」の英語表現の2つ目は「dissension」です。「dissension」の意味は「意見の相違」です。例文は、「they found dissension in their own ranks(彼らは内部の意見の相違に気が付きました)」です。
「軋轢」の英語表現③collision

「軋轢」の英語表現の3つ目は「collision」です。「collision」の意味は、「(利害・意見・目的などの)対立」「衝突」「激突」「不一致」です。例文は「a collision of sentiments(感情の衝突)」「a collision of views(意見の衝突)」です。
「軋轢」の英語表現④discord

「軋轢」の英語表現の4つ目は「discord」です。「discord」の意味は、「不一致」「仲たがい」「不和」「内輪もめ」「不協和音」です。「There seems to be some discord between them.(彼らは仲たがいしているようだ)」が例文になります。
「軋轢」の英語表現⑤strife
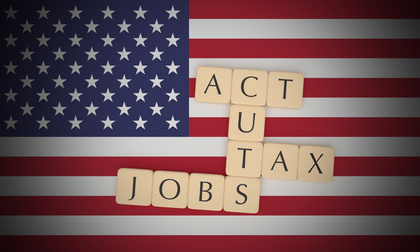
「軋轢」の英語表現の5つ目は「strife」です。「strife」の意味は「闘争」「争い」「紛争」です。「Strife is the rock on which the party split.(内紛が党の分裂したもとです)」が例文になります。「party」は「政党」という意味もあります。
「軋轢」の英語表現⑥clash

「軋轢」の英語表現の6つ目は「clash」です。「clash」の意味は、「不調和」「衝突」「不一致」「小競り合い」「釣り合わない」などになります。例文は、「Principles often clash with interests.(主義と利益というものは、しばしば衝突します)」になります。
軋轢の言葉の語源って?
「軋轢」の語源とは車輪がきしるという意味

「軋轢」の語源は「車輪がきしること」からきています。「軋」は「押し付ける」や「こすって音を出す」、「きしむ」、「あらそう」という意味です。「轢」は「もめる」や「車でひく」、「きしむ」という意味があります。この2つの文字の意味が組み合わさって「軋轢」という言葉になりました。
語源そのままの意味もある!「軋轢」のもう1つの意味

「軋轢」には「仲が悪くなること」のほかにもう1つ意味があります。それは「車輪のきしる音」です。つまり語源がそのままの意味として使われているのです。語源そのままの「車輪のきしること」という意味で使うことは多くはありませんが、「軋轢」イコール「車輪のきしる音」の意味でも使われているのです。
読みにくくても知っておきたい!「軋轢」の意味と使い方
「軋轢」という言葉は新聞や雑誌でもよく見かけますが、「書いてみてください」といわれたらちょっと難しいと思ってしまう言葉です。「軋轢」の「軋」も「轢」も他の言葉として見かけることはあまりなく、せいぜい「轢死」くらいのものです。「軋轢」の語源もあまり知られていません。少しとっつきにくい言葉ではあります。
「軋」も「轢」も書きにくい難しい漢字ではありますが、頻繁に使われる言葉なので、語源は知らなくても、少なくとも「軋轢」という言葉の意味自体はしっかり押さえておきたいものです。「軋轢」という言葉の意味そのものはそんなに難しいものではありませんが、「確執」との微妙な使い方の違いもあります。
そういった日本語の言葉の微妙なニュアンスというものは、付け焼き刃で身に着けることは簡単ではありません。やはり本を読む習慣が大切であり、ネットで調べることもできますが、本を読まないと使い方まではなかなか身につきません。日本語は繊細な言語ですので、侮らず言葉の意味や使い方に真摯に取り組みたいものです。
商品やサービスを紹介する記事の内容は、必ずしもそれらの効能・効果を保証するものではございません。
商品やサービスのご購入・ご利用に関して、当メディア運営者は一切の責任を負いません。
![chokotty[ちょこってぃ]](https://cktt.jp/assets/common/cktt_logo_PC_2-40c5a35e8da64f225f3dcdf1b548a3f3373f85eeab336668a1c00fe9a8ab42c8.png)










