煩悩の意味とは?煩悩の数が108つな理由と一覧・除夜の鐘との関係性も
煩悩の数が108もある理由を知っていますか?大晦日で年越しに向けて除夜の鐘を鳴らす時、108も叩くのが一般的とされていますが、それにこだわる理由は意外に知られていません。そんな煩悩について、様々な諸説や一覧を紹介します。
※商品PRを含む記事です。当メディアはAmazonアソシエイト、楽天アフィリエイトを始めとした各種アフィリエイトプログラムに参加しています。当サービスの記事で紹介している商品を購入すると、売上の一部が弊社に還元されます。
目次
煩悩の意味とは?
煩悩の意味とは「自分の精神を乱す欲望」

煩悩の意味とは、自らの身や心にまとわりつく苦しみや穢れ、誘惑といった精神を乱す欲望を指します。根源とも言える主な煩悩として三毒が存在しており、それぞれ、むさぼり求める欲望の「貪(とん)」、怒りの心である「瞋(しん)」、愚かな様子の「痴(ち)」があります。
この言葉は古代インドで使われていた言語である、サンスクリット語の「クレーシャ」という、「心の汚れ」や「苦しむ心」という意味を持つ言葉を原語に生まれました。
主に仏教で使われている言葉

仏教では人が苦む原因は煩悩にあると考えています。それらから克服するために、煩悩から解放される解脱をして、悟りの境地(涅槃)へ向かう行為が求められました。
仏教を開いた釈迦が死去した後に誕生した部派仏教の時代になると、煩悩に対する分析が行われ、煩悩を否定しないという考えが誕生しました。煩悩に対する2つの思想は、衆生救済を目的とした大乗仏教に影響を与えました。
煩悩の数は宗派によって異なる

現代の日本では、煩悩の数は108あるのが一般的とされていますが、時代や宗派によっては数が前後します。最も少なくて3つ、最大で84,000あると言われています。
また、仏教が生まれた時代から何百年も後に煩悩について細かく分析されていますが、その発想から、突き詰めていけば無限に存在するという考えが存在します。
煩悩の数が108つな理由の諸説4選
煩悩の数が108つな理由の諸説①迷いが生じる六根に関係がある

煩悩の数が108つな理由の諸説1つ目は、迷いが生じる六根に関係がある説です。六根とは、物事をみる「眼」、音や声を聞く「耳」、匂いを嗅ぐ「鼻」、口に含んだものを味わう「舌」、触れたものを感知する「身」、仏法を理解する「意」のことを指します。これらをもとに煩悩が存在するため、まず6通りあります。
六根が感じるものには、自身にとってよいものの「好」、悪いものの「悪」、どうでもいいものの「平」という3種類の「好悪」があります。これらを組み合わせた18通り(6×3)に、浄染という、穢れのない「浄」と穢れがある「染」も組み合わさるため36通り(18×2)の煩悩が生まれます。
これらの煩悩は、前の人生である「前世」、今の人生である「現世」、次の人生である「来世」に渡って人を苦しませるため、108通り(36×3)の煩悩が存在するということになります。このように、六根から煩悩が生まれる説を六根説と言います。
煩悩の数が108つな理由の諸説②四苦八苦という四字熟語から

煩悩の数が108つな理由の諸説2つ目は、四苦八苦という四字熟語からという説です。この四字熟語は「非常に苦労すること」という意味を持ちますが、仏教では「生老病死」という梱包的な苦しみである四苦を加え、愛別離苦などの四苦を合わせた八苦をまとめた言葉として使われています。
- ・生:生まれること。
- ・老:体力と気力が衰え、老いていくこと。
- ・病:病気にかかり、痛みや苦しみに悩むこと。
- ・死:死ぬことへの恐怖や不安。
- ・愛別離苦(あいべつりく):愛するものと別れること。
- ・怨憎会苦(おんぞうえく):恨めしい人や憎んでいる人に出会うこと。
- ・求不得苦(ぐふとくく):求めるものが得られないこと。
- ・五蘊盛苦(ごうんじょうく):人の肉体と精神が思うようにならないこと。
仏教における四苦八苦の種類
そして、四苦八苦を「四苦」と「八苦」に分けて掛け算にすると「4×9」と「8×9」になり、それぞれ答えが「36」と「72」になります。この二つの数字を足すと108になるため、四苦八苦から108が生まれたとされています。
煩悩の数が108つな理由の諸説③1年の月日

煩悩の数が108つな理由の諸説3つ目は、1年の月日です。1年には12の月と、季節を24等分した二十四節気と、二十四節気をさらに3つに分けた七十二候があります。これらを足すと、「12+24+72=108」になるため、108は1年を表した数字であると言われています。
煩悩の数が108つな理由の諸説④8という数字に意味があるから
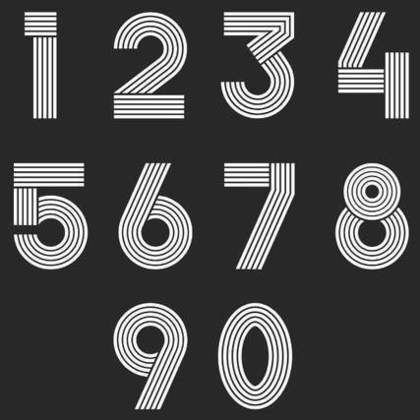
煩悩の数が108つな理由の諸説4つ目は、8という数字に意味があるからという説です。日本では昔から8という数字に「たくさんの」という意味を持たせていました。
その根拠に、「八百万の神」という言葉は実際に800万も存在しているという意味ではなく、それぐらい神様は多数存在しているという意味で使われています。つまり、煩悩は本当に108もあるのではなく、それぐらい存在するという意味が込められていると言われています。
煩悩の数の種類一覧9選
煩悩の数の種類一覧①貪(とん)

煩悩の数の種類一覧1つ目は貪(とん)です。サンスクリット語の「ローバ」や「ラーガ」から由来しているもので、必要以上に求める心を指します。また、貪欲(とんよく)とも呼ばれます。
仏教において克服すべき三つの煩悩(三毒)の一つで、人間の諸悪や苦しみの根源とされています。一般的な言葉に翻訳すると「欲」や「むさぼる」と表現されます。
煩悩の数の種類一覧②瞋(しん)

煩悩の数の種類一覧2つ目は、瞋(しん)です。サンスクリット語の「ドヴェシャ」から由来しているもので、怒りや憎しみの心を指します。また、瞋恚(しんに)とも呼ばれます。
三毒の一つとされていますが、瞑想修行を邪魔する障害である「五蓋(ごがい)」の一つでもあります。瞋から解放される方法として、釈迦は息子に「慈悲の瞑想を深めなさい」と説いています。
煩悩の数の種類一覧③癡(ち)

煩悩の数の種類一覧3つ目は、癡(ち)です。サンスクリット語の「モーハ」から由来しているもので、心理に対する無知の心や愚かな様子を指します。また、愚癡(ぐち)や我癡(がち)とも呼ばれます。
貪と瞋と一緒に三毒として数えられており、時には無知の状態である無明(むみょう)と動議にされる場合もあります。十二因縁の一部としても扱われており、豚のシンボルで描かれています。
煩悩の数の種類一覧④惛沈(こんじん)・睡眠(すいめん)

煩悩の数の種類一覧4つ目は、惛沈(こんじん)・睡眠(すいめん)です。惛沈は心身が疲れている様子の倦怠を、睡眠は活動を停止させる眠気を指します。どちらも瞑想修行を邪魔する五蓋の一つに数えられています。また、サンスクリット語では、前者は「スティヤーナ」で、後者は「ミッダ」となります。
煩悩の数の種類一覧⑤掉挙(じょうこ)・悪作(おさ)

煩悩の数の種類一覧5つ目は、掉挙(じょうこ)・悪作(おさ)です。前者は心が高ぶって血が上っている状態を、後者は過去に起きた出来事を思い出して後悔することを指します。
どちらも五蓋の一つとされていますが、掉挙は同じく五蓋である惛沈の対義語で、この二つは平常な心ではない状態のため、煩悩と認知されています。また、サンスクリット語では、掉挙は「アウッダティヤ」、悪作は「カウクリトヤ」とされています。
煩悩の数の種類一覧⑥疑(ぎ)

煩悩の数の種類一覧6つ目は、疑(ぎ)です。疑念や躊躇といった意味のサンスクリット語「ヴィチキッツァー」からきており、心理に対して疑っている心を指します。この状態では、いかなる教えも受け付けないとされています。
五蓋の一つですが、四諦の教えの中にある「躊躇」と定義されていたり、大乗仏教における煩悩心所の一つでもあり、パーリ経典における十結の一つでもあります。
煩悩の数の種類一覧⑦有身見(うしんけん)

煩悩の数の種類一覧7つ目は、有身見(うしんけん)です。修行者を欲界へと縛り付ける「五下分結(ごげぶんけつ)」の一つで、物の捉え方から考え方といったあらゆる面の中で自分を中心として考えていることを表す「我執」を意味します。また、五悪見の一つともされています。
煩悩の数の種類一覧⑧慢(まん)

煩悩の数の種類一覧8つ目は、慢(まん)です。サンスクリット語の「マーナ」に由来する言葉で、他人と比較して思い上がる様子や人を侮る心を指します。また、比較せずに自惚れている状態を憍(きょう)と言います。
煩悩の数の種類一覧⑨色貪(しきとん)

煩悩の数の種類一覧9つ目は、色貪(しきとん)です。色界に対する欲望や執着を表す煩悩を指し、五上分結のひとつとされています。
色界とは仏教における三界の一つで、欲望を離れた物質の世界を指します。そこに住む人は天人と呼び、食欲と淫欲を断じています。
煩悩の数と除夜の鐘をつく回数との関係性・同じ数な理由は?
煩悩の数と除夜の鐘をつく回数との関係性の理由は煩悩を祓うため

煩悩の数と除夜の鐘をつく回数との関係性の理由としては、煩悩を祓うためと言われています。人は108もの煩悩を持っていると言われているため、それらを祓うための儀式として、大晦日に除夜の鐘を108回ついて一つずつ消しているとされています。
また、除夜の鐘には汚れや苦悩などを祓う力があるため、信仰心を持っていなかったり、修行を積んでいない一般人でも効果があると言われています。
除夜の鐘のつき方は寺院によって異なる

ほとんどの寺院では鐘を108回つくのが一般的とされていますが、年が開ける前に鐘をつききる所もあれば、107回ついて最後の1回を新年につく所もあります。しかし、108にこだわらずに、鐘を200回以上つく所も少なくありません。
煩悩を捨てることの意味・必要性は?
煩悩を捨てることの意味・必要性①欲に対する執着を捨てる

煩悩を捨てることの意味・必要性1つ目は、欲に対する執着を捨てることです。一般的に煩悩は「欲=悪」と認識されていますが、元々仏教の教義には「欲=生きる力」と表記されています。つまり、欲を持つことを否定していません。
しかし、その欲に執着しすぎると感情などがコントロールできなくなり、周囲に害を与えてしまいます。なので、自分の身にあまるほど求めてはいけないという戒めになります。
煩悩を捨てることの意味・必要性②怒りや恨みを抑える

煩悩を捨てることの意味・必要性2つ目は、怒りや恨みを抑えることです。自分に害を与えた人に対する怒りや、自分が無視されたという恨みを持っていると、他人を傷つける原因になります。
周囲の人に対して慈しみの心を持って考えることで、自分の中に溜まった怒りや恨みは消え去ります。これにより、無意識に危害を加える行為も無くなります。
こちらの記事では、淡白な人の内心や理由についてまとめられています。淡白な対応をしている人は、プライドが高いといった特徴を持っています。このような特徴を捉えていれば、恋人に対して怒りを持つこともないでしょう。こちらの記事を読んで、淡白になっている理由を学びましょう。
煩悩を捨てることの意味・必要性③正しい知識を得る

煩悩を捨てることの意味・必要性3つ目は、正しい知識を得ることです。何も知らない状態で生活すると、人に対して偏見を持ったり、必要な行動を誤解したりします。
これらを避けるには、日頃から知識を取り入れて、何故この人はこういう考えを持っているのか、この行為に何の意味があるのかという疑問を解決しなければなりません。また、ただ吸収するだけでなく、自ら考える力も重要です。
煩悩は抑えられる!
煩悩といえば欲望そのものを指すと思われがちですが、本当は行きすぎた欲を意味します。全てを抑えるのは難しいですが、少しでも抑えることで生活にゆとりが生まれます。一度瞑想などをして、心を落ち着けてみましょう。
商品やサービスを紹介する記事の内容は、必ずしもそれらの効能・効果を保証するものではございません。
商品やサービスのご購入・ご利用に関して、当メディア運営者は一切の責任を負いません。
![chokotty[ちょこってぃ]](https://cktt.jp/assets/common/cktt_logo_PC_2-40c5a35e8da64f225f3dcdf1b548a3f3373f85eeab336668a1c00fe9a8ab42c8.png)










