性悪説とは|正しい意味・訳・読み方・誤用は?性善説との違いも
性悪説と性善説の間には、どのような違いがあるのでしょうか。「人の性は悪なり」とする性悪説には、誤用されることも多く、正しい意味を分かっていない人もいるかもしれません。性悪説とは人間のどのような面を表現しているのか、詳しく見てみることにしましょう。
※商品PRを含む記事です。当メディアはAmazonアソシエイト、楽天アフィリエイトを始めとした各種アフィリエイトプログラムに参加しています。当サービスの記事で紹介している商品を購入すると、売上の一部が弊社に還元されます。
「性悪説」の正しい意味・訳・読み方とは?
性悪説の意味とは:人間の本質は悪であるとする説

性悪説は、人間の本質が悪であるという説です。読んで字のごとく、生まれたときには天使のような無垢ではなく、悪の種を宿しているということです。ただし、この「悪」は「悪行」ではなく、人間が欲望を持っている存在であることを示しています。
性悪説の読み方:「せいあくせつ」

性悪説の読み方は「せいあくせつ」で、珍しい読みですね。「性悪」という言葉自体は「しょうわる」と読むことがありますし、このような読み方をすると、心根が腐った悪い人間という意味になってしまいます。「せいあく」と読むのはかなり特別な場合だけであり、「しょうわる」とは少し異なる意味を持っています。
性悪説に人間性や心根は関係ありませんので、当然、読み方が違えば意味も変わってしまいますね。実際に、「しょうわる」にちかい意味で誤用されることもありますが、誤解です。「せいあくせつ」の読みは慣れないかもしれませんが、こちらが正しい読み方なので、性悪説の内容と共に間違えないように覚えておきましょう。
性悪説の成り立ち:荀子の「人之性悪」の訳が原典
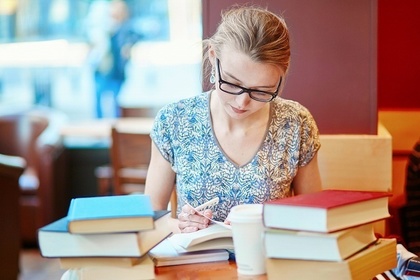
性悪説は、最初から「性悪説」として知られていたわけではありません。こちらは、儒学者の荀子の「人乃性悪」という論語が訳されたものとなっています。荀子は、人間の理想の姿よりも、現実的な姿を見た思想家とされています。紀元前3世紀ころの話ですが、よく比較対象とされる性善説よりは後となります。
性悪説の誤用:人間を「悪」しか持たない存在と考えるのは間違い

性悪説の誤用は後を絶ちませんが、そういった誤用の一つ目としては、人間を悪しか持たない存在だとみなすものが挙げられます。性悪説は、人間の全ての素質を悪だと断定しているわけではありません。また、自然状態では常に悪行ばかりすると言っているわけでもありません。これは完全に性悪説の誤解ですね。
性悪説が人間が悪意の塊であると断定している説なら、この世の中には絶望しかなくなってしまいます。これは荀子の考え方からも乖離していますね。悪人ばかりと考えるには、この世には優しい部分が残っていますからね。そうした人間の優しさを否定するような説ではないことは、頭に入れておいた方が良いかもしれません。
性悪説の誤用:人を疑えという意味ではない

性悪説は社会の中では誤用されることが多くありますが、その誤用の二つ目は、「人は疑うべき」という意味で使っているというものです。性悪説は確かに言葉の響きだけで言うと、この世の中に悪い人間が溢れているように思えてしまいますよね。強く理性を持っている人間しか、この世に良い人はいないように思えるでしょう。
そのような状態を指している言葉だとすれば、確かに人を疑うように諭されているように思っても仕方ありません。ですが、性悪説は他人に対する信用に関しては一言も述べていません。むしろ、成長とともに良い人が増えて行くのですから、信用問題はまた別の話になりますよね。人への信用を性悪説で語ることはできません。
性悪説の考え方とは?
性悪説の考え方➀「人の性は悪なり」の悪は「欲がある弱い存在」

性悪説の考え方の一つ目は、荀子の言葉にある通り、「人の性は悪なり」というものです。人間は生まれたときには「悪」の状態であるということです。ただし、この「悪」は悪行という意味ではありません。もちろん、そのまま育てば悪行に手を染めるようになりますが、赤ん坊がその素質を持っているということではないのです。
性悪説で、人間が生まれながらに持つ悪の種とされるのは、「自分を優先してしまう欲望」です。簡単に言うと、自己中心的であるということですね。確かに、小さなころは、自分の欲望のために他の人が動いてくれると思っているでしょう。また、望みが通らなければ泣いてしまうところもありました。
成長とともにこうしたところはなくなりますが、人間が元から持っているのは、自分の欲望を優先させようとする精神的な弱さということになります。この弱さを悪として扱うのが性悪説です。決して、最初から犯罪をしてしまうような凶悪な人間であると言っているわけではないのです。
性悪説の考え方➁成長や理性によって利他行動や善行を学ぶ

性悪説の考え方の二つ目は、成長や理性によって利他行動や善行を学ぶというものです。精神的に弱く欲望に負ける存在として生まれてくる人間ですが、成長過程の中での変化は不可能ではありません。人間は社会の中で生きていますから、成長とともに、自分よりも他者を尊重することもできるようになっていくのです。
最初から他人に親切にしようという子供はいませんが、成長していく中で「善の心」を学ぶと、すぐに変わることができるのは面白いですよね。環境に適応していく能力として、きちんと自分の欲を理性によって抑える術を知っていくのです。これにより、性悪説が「悪人ばかりの世」を嘆いているわけではないことが分かりますね。
性悪説の考え方③教育によって善を身に付けることができる
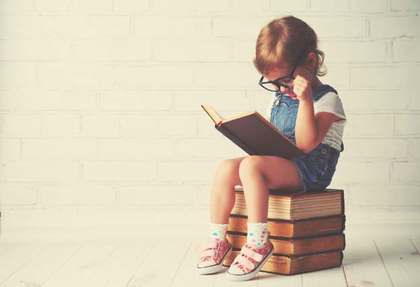
性悪説の考え方の三つ目は、教育によって善を身に付けることができるというものです。性悪説では、人間が欲をコントロールし、他者を尊重する存在になれると示唆しています。そして、それに必要なのが教育だとも述べています。荀子は決して夢想家ではありませんでしたから、人間が自然と善を学ぶとは思っていませんでした。
大人になり理性を身に付けて、自分の中の弱い部分を押さえることができるのは本当ですが、それは環境にも左右されてしまいます。導いてくれる人間がいなければ、人間の精神は成長しないということでもあります。「人間全てが悪」と誤解されやすい性悪説が、実は教育の大切さを説いているものだというのは面白いですね。
性悪説の考え方④悪行はしてはいけないと考える

性悪説の考え方の四つ目は、本当の意味での悪は認めないというものです。性悪説を誤解している人たちにしてみれば、驚きなのではないでしょうか。性悪説の中では、「悪は悪」として扱われています。犯罪や悪行を「仕方のないこと」としているわけではありません。これは、悪の捉え方からして間違っているのです。
荀子自身は、教育の重要性を解いて、人間は善の気持ちを学習するべきだとしました。決して悪を見逃して良いとは言っていないのです。また、悪いことをする心を肯定しているわけでもありません。また、悪行を行う人間に理解を示していたわけでもありません。
性悪説と性善説との違いは?
性善説と性悪説の違い➀性善説を唱えたのは孟子
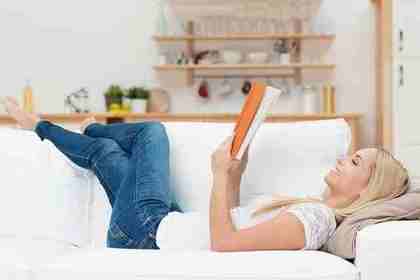
性善説と性悪説の違いの一つ目は、まずは提唱した人間が違うというところが挙げられるでしょう。性善説の提唱者は儒学者の孟子ですが、荀子よりも名前は有名かもしれませんね。順番としては、孟子の唱える性善説があり、それに異論を唱える形で性悪説が生み出されました。性善説の方が先なのです。
性善説と性悪説の違い➁人間の本質が善だと考えるのが性善説

性善説と性悪説の違いの二つ目は、性善説では人間の本質を善だと考えるというものです。この場合の善というのは、生まれながらにして「正しい行動をする」気持ちを持っているという意味ではありません。性善説においては、赤ん坊は無垢な存在で、汚れたところがないものだとしています。これを善と呼びます。
子供のころには、汚れや悪を知らない存在であり、このまま育てば一点の曇りもない「善の心を持つ存在」となるわけです。性善説は、大人も含めて人間の善を信じているかのように誤用されますが、これは間違っているということですね。あくまで、生まれたとき、子どものころに無垢で純粋な存在であったとするだけです。
要するに、生まれながらにして人に悪意を及ぼす悪魔のような存在の子どもはいないというだけのことであり、悪の存在を否定するわけではありません。性善説は楽観的であると批判されることもありますが、そもそも、人間の善なる心を無垢な赤ん坊にのみ認めるのが性善説です。そのため、楽観的とする批判は的外れでしょう。
性善説と性悪説の違い③人間の成長の過程で身に付けるものが異なる

性善説と性悪説の違いの三つ目は、人間の成長の過程で身に付けるものに違いが表れるというものです。性善説と性悪説は、生まれたときに人間が持っている本質という意味で違いがあります。ですが、人間が成長していく過程で変化すると言う考え方自体に違いはありません。ただし、身に付けるものは異なります。
性善説は、成長とともに心に汚れが付着するとしています。要するに、悪の心を身に付けるのです。純粋で無垢な存在だった人間が欲望によって汚れを知り、汚れた心を他者から隠そうとする行動こそが悪だとするのが性善説です。成長の過程で善という希望を身に付けるのが性悪説と考えると、かなり違いますね。
もっとも、成長と共に悪の心を身に付けることを「仕方ない」と諦めるべきだとは孟子は言っていません。これは避けるべきだという考えはもちろんありますが、性悪説が教育を重視していたのに対し、性善説では教育の重要性を説いているわけではありません。性善説においては、心を守る強さが重要視されます。
性悪説について正しい知識を手に入れよう!
「人の性は悪なり」と唱えた性悪説を誤用している人は珍しくありません。「人の性は悪なり」という言葉を現代的に解釈すると、周囲の人間を信用してはいけないと言っているように聞こえてしまいますが、それは正しくないのです。むしろ、性悪説は、成長とともに善の心を身に付けるという希望のある説ですよね。
「人の性は悪なり」という言葉を直接的に解釈しないよう、しっかりと性悪説についての正しい知識を身に付けておきましょう。誤用し続けることで話が通じなくなってしまうこともあるので注意してくださいね。また、一緒に、性善説についてもきちんとした知識を身に付けておくのは良いことなのではないでしょうか。
「人の性は悪なり」の「悪」が悪行ではなかったとしても、この世の中には「しょうわる」な人間もたくさんいますよね。そんな人間は、成長の過程で、きちんとした理性を身に付けてこなかったということなのかもしれません。現代的な解釈での「人の性は悪なり」な人間について知りたい方は、以下の関連記事をご覧くださいね。
商品やサービスを紹介する記事の内容は、必ずしもそれらの効能・効果を保証するものではございません。
商品やサービスのご購入・ご利用に関して、当メディア運営者は一切の責任を負いません。
![chokotty[ちょこってぃ]](https://cktt.jp/assets/common/cktt_logo_PC_2-40c5a35e8da64f225f3dcdf1b548a3f3373f85eeab336668a1c00fe9a8ab42c8.png)









