釈迦に説法のことわざの意味は?類語や逆の意味の言葉・使い方も
釈迦に説法ということわざの意味をご存知ですか?専門家ともいえるお釈迦様に、わざわざ説法をしてしまうことには、どのような意味が隠されているのか気になりますね。類語や、逆の意味の言葉も調べながら、適切な使い方を考えてみましょう。
※商品PRを含む記事です。当メディアはAmazonアソシエイト、楽天アフィリエイトを始めとした各種アフィリエイトプログラムに参加しています。当サービスの記事で紹介している商品を購入すると、売上の一部が弊社に還元されます。
目次
釈迦に説法のことわざの意味は?
釈迦に説法のことわざの意味①しゃかにせっぽうの釈迦は仏教の開祖のこと

釈迦に説法(しゃかにせっぽう)のことわざの意味の1つ目は、ことわざに含まれる「釈迦」についてです。釈迦は仏教の開祖のことを意味します。35歳で悟りを開き、80歳で亡くなるまでに、仏教の教えを説いてまわっていたと伝えられている人物です。現在の仏教の修行法や、悟りを開くための道筋などを築き上げました。
ちなみに、釈迦の語源は、お釈迦様の出身である部族の名前にあります。正しくは「釈迦牟尼(しゃかむに)」と言い、牟尼は聖者を意味します。お釈迦様とは、釈迦族の聖者という意味だったんですね。長い修業の末に悟りを開き、仏教の開祖となった人物ですから、聖人として扱われるのも納得です。
釈迦に説法のことわざの意味②しゃかにせっぽうの説法は教えを説くこと

釈迦に説法のことわざの意味の2つ目は、ことわざに含まれる「説法(せっぽう)」についてです。こちらは、仏教の教えを説いて聞かせることを意味します。仏教における説法は、物事の道理を、相手の理解力に応じて説明していくことです。
転じて、自分の考えを相手に教えて、言い聞かせることを意味します。現在では、仏教だけに限られず、どのような意見や教えでもOKという幅広い解釈がされています。
説法(せっぽう) ① 仏の教えを説いて聞かせること。 ② 意見すること。自分の考えを相手に言い聞かせること。
引用元: Weblio辞書
釈迦に説法のことわざの意味③その道の専門家に教える愚かさを例えること

釈迦に説法のことわざの意味の3つ目は、その道の専門家に教える愚かさを例えることわざだということです。釈迦は仏教の開祖ですね。すべての教えは、釈迦が修行の末に悟りを開き、会得したものです。つまり、お釈迦様以上に、仏教のことについて詳しい人物はいないのです。
お釈迦様に説法をすることは、それだけ愚かな行為だということですね。その道の専門家に、素人が意見する様子を想像してみてください。だいぶ、いたたまれないですね。仏教だけに限定されず、どのような分野にも該当することわざです。
仏教から派生した言葉は、「釈迦に説法」だけではありません。こちらの記事で紹介されている「諸行無常」も、もとは仏教の言葉なので、詳しくチェックしてみてくださいね。深い意味が隠されていますよ。
釈迦に説法のことわざの類語5選
ことわざの類語①釈迦に経

ことわざの類語の1つ目は、「釈迦に経(きょう)」です。経と言えば、お寺でお坊さんが唱えている、お経ですね。こちらのことわざの意味を考えるためには、まず「経とは何か」という点に触れなければいけません。
お経とは、仏教における聖典のことで、お釈迦様の説法を文字として記録したもののことです。つまり、お経に書かれていることは、すべてお釈迦様が口にしたものばかりなのです。口で伝えるか、文字で伝えるかの違いですが、「釈迦に説法」と全く同じ意味の類語となる表現です。
ことわざの類語②孔子に悟道
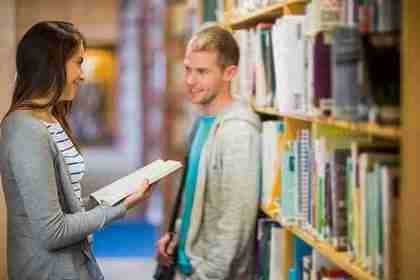
ことわざの類語の2つ目は、「孔子(こうし)に悟道(ごどう)」です。孔子は、紀元前551年~479年に存在した中国の思想家で、儒教の開祖でもある人物です。弟子との問答を記した「論語」で知られていますね。仁という人間愛や、道徳についての考えが、短い文章にまとめられています。
「悟道」は、悟りの道や道徳を指していう言葉です。孔子がよく知っている内容のものとなりますね。孔子に道徳を説くように、素人が専門家に教えることの愚かさを例えています。「釈迦に説法」とセットで、一つのことわざとされることもある類語です。また、「孔子に論語」という言い方がされることもあります。
ことわざの類語③河童に水練

ことわざの類語の3つ目は、「河童(かっぱ)に水練(すいれん)」です。河童とは、日本の伝説上の生き物のことですね。頭の皿と、背中の甲羅、手足の水かきが特徴です。その姿から分かるように、川の中に住むと考えられています。また、「水練」とは、水泳の練習を意味する言葉です。
水中の生き物である河童に、泳ぎを教えようとすることに関係する言葉なんですね。河童が泳ぎのプロであるように、その道の専門家に教えることの愚かさを例えている類語です。
ことわざの類語④猿に木登り

ことわざの類語の4つ目は、「猿に木登り」です。これまで紹介した類語のパターンから、意味を察することができますね。猿といえば、木登り上手であることに間違いないですね。こちらの場合は、木登りのプロに、木登りを教える様子が関係します。
猿は、生まれたときから木登りのことをよく知っています。教える必要がない相手に、教えようとする愚かさを例えている類語です。
ことわざの類語⑤極楽の入り口で念仏を売る

ことわざの類語の5つ目は、「極楽(ごくらく)の入り口」で念仏を売る」です。極楽とは、あらゆる苦しみや災のない、安らかな世界のことを意味します。仏教において、人が死後に向かう先ですね。しかし、死んだあとに、誰でも極楽浄土に入ることができるわけではありません。
極楽に行くには、「念仏を実践する」という条件を満たしていなければいけないのです。逆に考えると、極楽の入り口にいるのは、すでに念仏を実践し、極楽に入る条件を満たしている人たちばかりなのです。念仏を知り尽くしている人たちに、念仏は必要ありませんね。
よく知っている人に、物を教えようとすることを例えている類語です。何の役にも立たないことを、しようとしているときにも使われます。
釈迦に説法のことわざと逆の意味の言葉5選
逆の意味の言葉①馬の耳に念仏

逆の意味の言葉の1つ目は、「馬の耳に念仏」です。念仏は、極楽浄土に行くための有り難いものですが、馬がそのようなことを理解するはずがありません。いくら目の前で唱えようとも、相手が馬では全くの無意味です。
転じて、いくら人が意見しても、聞く耳を持たないことを意味します。どんなに忠告しても、全く効き目がないことを例えていう言葉ですね。「釈迦に説法」では、相手が立派すぎるため、意見する方が愚か者として扱われます。また、意見する方が提供する説法なども、価値のない拙いものであると解釈されます。
「馬の耳に念仏」では、相手を愚か者として扱い、意見する方が立派な立場であるように扱います。また、意見する方が提供するものも価値あるものとして捉えられます。確かに、逆の意味となる言葉ですね。
逆の意味の言葉②豚に真珠

逆の意味の言葉の2つ目は、「豚に真珠」です。真珠は価値ある宝石ですが、豚には、その価値は分かりません。つまり、価値の分からない者に、良いものを与えても何の役にも立たないことを意味します。
ちなみに、語源は新約聖書の一節にある言葉です。「豚に真珠を投げてはならない」という言葉に続き、「彼らはそれを踏みつけ咬みついてくるだろう」と記されています。聖書はキリスト教のものなので、宗教的にみても、「釈迦に説法」の逆といえる言葉ですね。
逆の意味の言葉③猫に小判

逆の意味の言葉の3つ目は、「猫に小判」です。小判は、昔のお金で、大変価値があるものです。日本銀行の資料によると、小判1枚は、13万円くらいの価値があるとされています。1枚だけでも、粗末にできませんね。しかし、猫にとっては、そんな価値も関係のないものです。
「豚に真珠」と同じように、価値の分からないものに、良いものを与えても無駄であることを例えている言葉です。猫にとっては、かつお節の方が、よほど嬉しいのかもしれませんね。
逆の意味の言葉④兎に祭文

逆の意味の言葉の4つ目は、「兎(うさぎ)に祭文(さいもん)」です。祭文とは、祭りのときに神さまに捧げる祝詞(のりと)のことです。災いを除き、幸せをもたらすために使われる、有り難いものです。
兎も、馬や豚、猫と同じように、有り難いものを理解できない動物として扱われています。兎に神さまのことを説いても無駄なように、いくら意見しても、なんの効果もないことを意味する言葉です。
逆の意味の言葉⑤牛に対して琴を弾ず

逆の意味の言葉の5つ目は、「牛に対して琴を弾(だん)ず」です。「弾ず」とは、楽器を弾いてはいけないという意味ですね。琴の名人が、牛に対して弾いて名曲を聞かせたという、中国の故事に基づいた言葉です。とても立派な演奏でしたが、牛は何の興味も示さず、ただ草を食べているばかりでした。
牛を志の低い人や愚かな人に例えて、そのような者に、高尚なものを与えても意味がないことを意味します。立派な話を説いても、愚か者に通じることはないという意味も持ちます。
釈迦に説法のことわざの使い方3選
釈迦に説法の使い方①専門家に意見していることを指摘する

使い方の1つ目は、専門家に意見していることを指摘するものです。相手の実力や経歴を知らず、いろいろと教えている場合に使えます。例えば、「彼女にテニスを教えるなんて釈迦に説法だよ。高校時代にインターハイに出たほどの実力なんだから」のような使い方が考えられますね。
指摘するのは心苦しいかもしれませんが、いずれ判明する事実であれば、早めの忠告をしてあげた方が良いでしょう。とくに、傍目から見ても、あまり実力がない人が教えようとしているときに用います。
釈迦に説法の使い方②ビジネスシーンなどで相手を立てる

使い方の2つ目は、ビジネスシーンなどで相手を立てるものです。仕事をするうえでは、特定の物事について、遥かに詳しい相手に何かを教えなければいけない場面もあることでしょう。
そんなときに、「◯◯さんにこの分野について話すのは、釈迦に説法でしょうが~」という一言を加えると、「あなたの方が素晴らしい」という意味で相手を立てることができます。
また、自分がその分野に詳しくても「皆さんにお教えするのは、釈迦に説法となりますが~」のような使い方で、「自分はたいしたことはない」と謙遜することも可能です。こちらも、相手を立てることにつながりますね。もちろん、ビジネス以外の場面で使ってもOKです。
釈迦に説法の使い方③皮肉として使う

使い方の3つ目は、皮肉として使うものです。例えば、「釈迦に説法は、やめておいた方が良いですよ」のような使い方は、ともすると「あなたは素人なんだから、人に教えるなんて愚かなことはやめておいた方が良いですよ」のような意味になりかねません。
「釈迦に説法」は、「よく知っている専門家」と「専門家には及ばない人」の二対で成り立っている表現だからです。使い方に注意しなければ、知らないうちに「あなたは物をよく知らないほうの人だ」と決めつけてしまうことになります。皮肉としての使い方にならないよう気をつけてくださいね。
人間関係を円滑に進めるためには、知らずしらずのうちに、相手を傷つけるような言い方をしないように注意しておく必要があります。うっかり使って皮肉となってしまう言葉を、押さえておきたいですね。こちらの記事の「ご愁傷様」も、使い方に気をつけておきたい言葉です。
釈迦に説法の使い方のポイントを押さえよう
「釈迦に説法」は、その道の専門家にものを教えることの愚かさを、例えるための表現ですね。語感が似ているためか、どんなに良い意見を言っても無駄という意味の「馬の耳に念仏」と、意味が混同されることがあります。表現は似ているかもしれませんが、まったく逆の言葉になるので注意しましょう。
また、使いどころも難しく、一歩間違えると皮肉のような表現になってしまいます。日常会話では、あまり使用する場面はないかもしれませんが、いざというときのためにポイントを押さえておくと安心できますよ。
商品やサービスを紹介する記事の内容は、必ずしもそれらの効能・効果を保証するものではございません。
商品やサービスのご購入・ご利用に関して、当メディア運営者は一切の責任を負いません。
![chokotty[ちょこってぃ]](https://cktt.jp/assets/common/cktt_logo_PC_2-40c5a35e8da64f225f3dcdf1b548a3f3373f85eeab336668a1c00fe9a8ab42c8.png)










