プライム案件とは?一次請けとの違い・客先常駐やベンダーとは
システム開発において耳にする機会のあるプライム案件に関して説明していきます。システム開発には多くの工程が必要であり、また様々な専門用語が使われています。一次請け、やベンダー企業、コントラクタ、などその言葉の意味や違いを解説していきたいと思います。
※商品PRを含む記事です。当メディアはAmazonアソシエイト、楽天アフィリエイトを始めとした各種アフィリエイトプログラムに参加しています。当サービスの記事で紹介している商品を購入すると、売上の一部が弊社に還元されます。
目次
プライム案件とは?一次請けとの違いも
プライム(prime)案件とは企業が顧客と直接契約を結ぶ一次請け案件

英語のprimeは「主要な、重要な」とか「優良な、最良な、第一等の」という意味になります。システム開発で使用されるプライム案件というのは、システムを開発する企業が顧客となるユーザーと直接契約するものをプライム案件と呼んでいます。
システム開発には多くの工程が必要となります。そのため作業が細分化されており、その工程をそれぞれ管理していくことが必要になります。この作業の細分化は建築業界と似ています。そのためユーザーとの直接取引をする窓口となる企業と各作業を請け負う下請け企業が存在します。
プライム案件と一次請け(元請け)の違いは案件の種類かどうか

プライム案件は顧客と直接契約により得た案件のことをプライム案件と呼びますが、その契約を行った企業を一次請け(元請け)と呼びます。一次請けという言葉の通り、開発内容によっては、二次請け、三次請けと、下請け企業に作業が割り振られます。
プライム案件と一次請けの違いは、システム開発を行う側の案件の位置づけと企業の立場の位置づけと言えます。一次請け(元請け)企業がプライム案件の窓口となると言えます。
プライム案件のメリット(企業の場合)
企業としてのメリット①中間マージン

利益を多く得ることができることです。顧客と直接契約をしているため、当然売り上げは全額一次請け企業が受け取ります。もちろん下請けに外注すればそれは経費となりますが、まず自社の利益を確保することができるというのは、企業としては大きなメリットです。
当然そこで働く社員にもそれは還元されるので、プライム案件を扱える企業で働くのと、そうでない場合の違いが出てくるのは否めないでしょう。
企業としてのメリット②顧客との交渉

システム開発における様々な取り決めに関して、主導権を握ることができます。納期や開発環境、場合によってはその後の保守・運用における窓口としての采配まで、交渉が可能となります。
同時にそれは顧客との関係が近くなるという面もあるので、顧客満足度を直に見ることができる、それを活かしていく事ができるというのも企業としてはメリットと言えます。
企業としてのメリット③アピール材料

自社が扱った製品として他企業にアピール材料として紹介することができ、且つ信頼を得ることができます。また、人員や工数等具体的に提示をすることもでき、類似案件などを扱う際には更なるアピール材料となります。
プライム案件を扱ってきた実績を材料に企業イメージを作り上げたり、他社との差別化を図ることもできます。扱う業種の違いや規模の違いが多くあれば、それだけユーザーには安心材料として提供することができます。
プライム案件のメリット(SEの場合)
プライム案件|SEとしてのメリット①大規模案件に携わることができる

上流工程に携わるという事は、全体をコントロールする側に携わることができるという点です。例えプロジェクトマネージャーの立場でなかったとしても、要件定義や設計に携わることで、全体を把握することができ、交渉術やスケジュール管理の能力を磨くことができます。
様々な業種や、様々なシステムに携わることができるという点もSEとしては、視野が広がり、考え方においても大局を捉えて細部に落とし込んでいくという発想を得られるはずです。
プライム案件|SEとしてのメリット②安定企業で働くことができる

プライム案件を請け負う企業は大企業であることがほとんどで、給与も高額なことが多く、福利厚生が充実しているという面も共通していると言えます。有名なプライムベンダーは誰もが知っているIBMやNTT、日立、NECなどです。
プライム案件のデメリット
プライム案件のデメリット①企業にとって
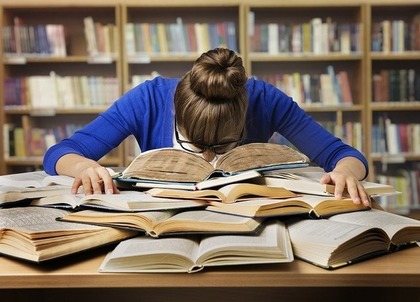
プライム案件に携わることのデメリットとしては、技術者としての能力向上に自主性が必要となる、ということが言えます。開発技術を仕事の業務で向上させる機会はほとんどないため、会社側も会社として主体的に技術者の育成に力を入れなければ、下手をすると、二次請けの企業の方がスキルが高い、ということもあり得ます。
プライム案件のデメリット②SEにとって

個人としても、その企業の看板がなくなれば、技術者としては能力不足となってしまいますので、IT業界で働き続けたいという希望があるのであれば、ある程度の技術スキルは自主的に身に付けたいところです。
システム開発の流れ
システム開発の流れとその規模による下請け構造について

システム開発を行う場合、いくつもの工程が必要になります。大まかな流れは、要件定義、基本設計、詳細設計、コーディング、単体テスト、結合テスト、システムテスト、リリースとなります。システムの規模によっては、この工程を一次請け企業で全て賄うことが難しく、その場合に下請け企業にこれら作業を依頼します。
一次請け企業はこの中の要件定義、基本設計に主に携わることとなり、ユーザーとのやり取りやスケジュール管理などのスキルが求められます。逆に二次請け、三次請け企業では素早いコーディング(プログラミング)スキル、膨大なテストを実施する人員が求められるという違いがあります。
企業としては絶対的にプライム案件を請け負う一次請け企業にメリットがありますが、一技術者としては、大規模案件の一次請けばかりを担当していると、開発スキルを身に付けることは難しくなります。もちろん、独学で勉強したり、スキルの高い技術者との交流で身に付けることはできます。
システム開発で求められるスキル①上流工程はヒアリング・要求分析力

システム開発では作業内容を上流工程と下流工程に分けます。この工程によって、必要とされるスキルには違いがあります。システム開発の流れでいう要件定義と基本設計がこの上流工程にあたります。要件定義の前にはユーザーのヒアリングや要求分析がありますが、ざっくりとその作業も要件定義としておきます。
要件定義の工程はユーザーが必要としているシステムがどのように実現できるか、またはどのようなシステムならばユーザーの業務効率化を促せるかという視点が必要で、その業種の業務内容に明るいことや、業務効率化のための問題定義ができれば、ユーザーの満足度が上がります。
要件定義で洗い出した内容を実際にシステム化していくための具体的な内容をまとめていきます。他システムとの連携が必要であれば、この段階でどのように実現していくかを検討することも必要になります。
システム開発で求められるスキル②下流工程はプログラミング技術力

下流工程にあたるのが、実際にプログラムを組んでいく作業となりコーディングと呼ばれる作業です。この作業は仕様書通りにプログラミング言語を組んでいく作業になりますが、技術の高い人が組んだコーディングは見た目にも美しく、後から他の人間が見返しても分かりやすいものが多くあります。
コーディング後、実際にシステムが動くかどうかの確認のためにテストの工程は細かく分かれています。まず、各機能毎に正常にプログラムが進んでいくかを確認するための単体テスト、そして他機能との連携が行われるかの結合テスト、最後にシステムとして設計書通りの動きをするかどうかを確認するシステムテストです。
テストの作業には忍耐力もかなり必要となりますが、このテストの工程で手を抜いたり、省いたりすると、製品として不十分なものになります。逆にいえば、このテスト工程で様々な不具合を洗い出すことができ、且つ解決することができれば、非常に品質の良い製品が出来上がります。
システム規模の巨大化や細分化による企業の役割の違い

私たちの日常に当たり前のようにIT(Information Technology)化が浸透しました。それに伴いシステム開発の規模は大規模なものから、小規模なものまで様々になりました。大規模システムの代表格は銀行や鉄道、官公庁で使用されるシステムです。
そのような大規模システムには、元請け企業、下請け企業という存在がどうしても必要になります。逆に小規模なシステムに関しては数名で開発が可能なシステムも存在するため、作業の分割ではなく、業務に詳しく且つ、システムに詳しい、ある程度マルチプレーヤーとなる人材が必要とされます。
プライム案件で客先常駐について
客先常駐は常駐される側に大きなメリットがある

読んで字のごとくですが、SE(システムエンジニア)やPG(プログラマー)が自社ではなく顧客先に常駐している契約形態を言います。
一口に客先常駐といっても、ユーザー企業の社内SEの役割を担う場合もあれば、一次請け企業にSEやPGとして常駐したり、はたまた三次請け企業が二次請け企業に常駐するという場合もあります。客先常駐は自社の業務ではなく、あくまでお客様先に出向いての業務のため、働き方に様々な意見があるのも実情です。
常駐される側は、システム部分で日頃疑問に感じていることや、改善の余地など、常駐者にざっくばらんに話を聞くことができる良いチャンスです。今まで通りのルーティン通りにシステムを作るのではなく、思い切って業務フローを見直すなど、新しい視点で意見が聞けるかもしれません。
客先常駐では業務への理解を示すことが求められている

顧客と直接契約を結んだ企業から、顧客側へSEを派遣する場合は、プライム案件で客先常駐をするということになります。これは顧客が自社以外での開発を望まない場合にはあり得えます。機密データを扱っているなど、決め事などが多い場合にもこういった形がとられることがあるようです。
プライム案件で客先常駐する場合は、そのSEの能力が問われます。その企業の業務に詳しい必要はありませんが、理解力やコミュニケーション能力、ちょっとした技術的アドバイスなど、派遣されたSE次第でその後の案件契約に違いが出てきます。
より客先にアピールするために、データに基づいた説明や、マニュアルの整備などは重要です。わかりやすいマニュアルの作り方の記事があるので、併せてご覧ください。
プライムベンダーとは
ベンダーとはシステムを設計・開発する企業

ベンダーとは英語のvendorを意味します。内容は商品や製品を販売、提供する事業者のことをいいます。システム開発においては、システムを設計・開発する企業になります。二次請け、三次請けの企業で、自社製品を扱っていない、開発のみを請け負う企業はベンダーには含まれません。
ベンダーの対義語として使われる単語には、ユーザー、エンドユーザーがあります。商品や製品を購入する側、ITで言えばサービスの提供を受ける側をそのように呼びます。
プライムベンダーとは一次請け・元請けのこと

プライム案件を扱うSier企業をプライムベンダーと呼びます。プライムベンダーは一次請け、元請けと呼ぶこともあります。多くのプライムベンダーは、世間的な知名度も高い大企業がほとんどです。
コントラクターとは
コントラクターとは開発を請け負う企業

コントラクターの英語表記はcontractorとなり、意味は請負人となりますが、システム開発で使用されるコントラクターは開発を請け負う企業を意味します。一次請け企業をプライムコントラクター、二次請け以降の企業をサブコントラクターと呼びます。
プライムコントラクター

プライムコントラクターはIT業界の有名ブランドと言えるでしょう。システム開発を依頼する場合に一極集中となることが多いです。ただシステム開発の分野は日々目まぐるしく変化しており、世界のレベルから遅れていると言われている日本は、このプライムコントラクターへの一極集中を見直す必要に迫られてもきています。
プライムコントラクターだから安心という事も言えなくなってくるかもしれません。その時には個々人のスキルが非常に重要になってきます。IT業界でどのような仕事に携わっていきたいかという目標をもって、規模の大小やプライム案件を扱っているというブランド力に惑わされないことも大切になります。
今後の仕事をしていく上で将来のビジョンを持つことはとても大切です。キャリアビジョンについての記事があるので、併せてご覧ください。
プライム案件を多く扱う企業で働くことはSEとして幅広い体験ができる
プライム案件を経験しないのと、経験するのとでは、当然経験した方が良いでしょう。それは仕事の全体像を捉えることができるからです。全体の流れやユーザーが要求することへの理解を深めることは、システム開発という業務に限らず、どのような仕事であっても必要な視点と言えます。
商品やサービスを紹介する記事の内容は、必ずしもそれらの効能・効果を保証するものではございません。
商品やサービスのご購入・ご利用に関して、当メディア運営者は一切の責任を負いません。
![chokotty[ちょこってぃ]](https://cktt.jp/assets/common/cktt_logo_PC_2-40c5a35e8da64f225f3dcdf1b548a3f3373f85eeab336668a1c00fe9a8ab42c8.png)











