推敲の言葉の意味を知ってる?使い方の例文・英語と故事の由来と口語訳も
「推敲」という言葉は「校正する」など他の類語表現と混同されやすく、また中国の故事に由来しています。ここでは文章等に対して行う推敲の意味やその言葉の使い方を例文をまじえて紹介しつつ、英語表現はどのようになっているのかという部分まで幅広く紹介していきます。
※商品PRを含む記事です。当メディアはAmazonアソシエイト、楽天アフィリエイトを始めとした各種アフィリエイトプログラムに参加しています。当サービスの記事で紹介している商品を購入すると、売上の一部が弊社に還元されます。
目次
推敲の言葉の読み方・意味は?
推敲の言葉の読み方は「すいこう」

推敲の言葉の読み方は「すいこう」です。推敲という言葉「推薦」「推挙」という言葉で使われる「推(すい)」と、「原稿」「初稿」といった言葉で使われる「稿(こう)」という漢字を合わせた熟語です。日本語の文章の中でよく使われる表現であり、難しそうな熟語ではあるものの一般的に使われている言い回しです。
推敲という言葉はそれぞれの漢字が一般的に使われている漢字であることから、日本でできた熟語であると思われがちなのですが、中国の故事成語に由来する言葉になっています。その由来等については後述していきますが、これは推敲という概念が古くから存在していたことを示す事実となります。
推敲の意味は誤字脱字や言葉遣いを含めた文章のチェックや練り直し
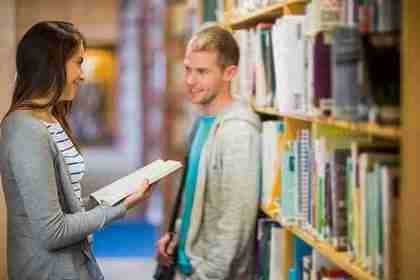
推敲の意味は、誤字脱字や言葉遣いを含めた文章のチェックや練り直しです。推敲という言葉は、「文章を推敲する」「レポートを推敲して再提出する」などといった形で使われますが、類語表現も多く存在するため、それらの類語表現との使い分けも非常に重要になってきます。ここではそんな使い分けや例文も紹介していきます。
推敲の言葉の使い方は?
推敲の言葉の使い方と例文①原稿を推敲する
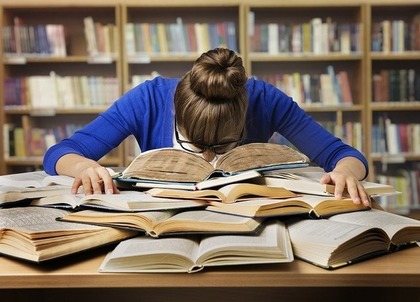
推敲の言葉の使い方と例文の1つ目は「原稿を推敲する」という表現を紹介します。原稿の推敲については様々な業種においてされていることであり、学生についても原稿の推敲をすることが少なくありません。例文としては「部下からあがってきた原稿を推敲する」といった形になります。
また「彼は粗削りで修正も多いが、原稿を推敲すると同じような修正は二度と受けないように注意し、進歩しながら原稿の質を上げてきている」といった形でも使います。推敲という言葉は原稿と一緒に使う場面が非常に多い言葉です。
推敲の言葉の使い方と例文②入念な推敲

推敲の言葉の使い方と例文の2つ目は「入念な推敲」という表現です。文章や原稿の練り直しや修正をする推敲という言葉において、軽く行う場合としっかりやる場合に分かれます。そのため「入念な推敲」という表現を使う場合には、時間をかけてしっかり内容を練り直していくような推敲が想定されます。
例文としては「この推薦文の出来で学生が希望の企業に就職できるか大きく左右されるので今入念な推敲を行っております」といった形になります。大事な場面での原稿や提出物は、その内容のクオリティが問われますので、「入念な推敲」という表現を使う場合には例文のように重要な場面の背景も説明すると説得力が生まれます。
推敲の言葉の使い方と例文③完璧に推敲されている

推敲の言葉の使い方と例文の3つ目は「完璧に推敲されている」を紹介します。「完璧に推敲されている」は「来週大手週刊誌に出す原稿は完璧に推敲されている」といった形で使います。推敲が完了した文章に対し、そのクオリティに自信がある場合には、例文のように完璧という言葉を使いながら状況を説明できます。
推敲が由来する故事の内容と口語訳は?
推敲が由来する故事の内容は「僧推月下門」という表現の手直し

推敲が由来する故事の内容は、「僧推月下門」という表現の手直しです。「僧推月下門」という漢詩があり、これは僧(僧侶)が月夜の夜に門を押す様子を表している場面になります。文章でこの場面を表すにあたり「押す」という表現が「敲く」なのか「推す」なのか、どちらの方が適した表現なのか、著者は迷ったのです。
月夜の夜というのはどちらも風情があり、この故事の場合においても文章にその風情を出したいという思いがありました。月夜の夜に門を「敲く」という表現になると、静寂の夜に門を敲く音だけが響くことになります。逆に「推す」にすると、僧は門を押すだけなので夜の静寂が強調されることになるのです。
しかし、門を「敲く」という表現もあえて門を敲く音だけが鳴り響いている場面を想像させることで、月夜の静寂を読み手に想像させることができます。こういった、「推す」なのか「敲く」なのか迷ったという故事成語のエピソードにより、「推敲」という言葉が生まれたのです。
推敲が由来する故事の口語訳は「僧は推す月下の門」

推敲が由来する故事の口語訳は「僧は推す月下の門」です。「僧推月下門」を日本語読みすると「僧は推す月下の門」となります。日本語の文法に当てはめるなら「僧は月下に門を押す」というのが正しい表現になりますが、「推敲」の由来を語る表現を読む場合には、この順番で読むことになります。
ちなみにこの故事成語ですが、賈島(かとう)という詩人がこの文章について「推す」がいいのか「敲く」がいいのかずっと考えていて、そのうちに韓愈という文人の行列にぶつかり捕らえられてしまうエピソードがあります。賈島が韓愈に事情を話したところ「敲の方が良い」という助言を韓愈からもらい打ち解けたのです。
推敲が含まれる四字熟語とその意味は?
推敲が含まれる四字熟語は「月下推敲」で中国漢詩に由来する

推敲が含まれる四字熟語は「月下推敲」で、中国漢詩に由来する表現です。「月下推敲」という言葉は先ほど表現した「僧は推す月下の門(僧推月下門)」に由来している表現であり、「月下推敲」という表現は、日本語表現において四字熟語として使われることもある表現です。
ちなみに「推敲」以外にも中国の漢詩に由来している熟語はあり、その一つが「杜撰」という言葉で、物事がいい加減な様を表す言い回しになります。下記の関連記事は「杜撰」に関して詳しく紹介したおすすめの内容になります。こういった記事を読むと由来や語源からその言葉の本質を理解することができ、おすすめです。
「月下推敲」の意味は何度も内容を練って書き直すこと

「月下推敲」の意味は、何度も内容を練って書き直すことです。「月下推敲」という四字熟語よりも、現在では推敲という言葉を使うことの方が圧倒的に多くなっていますが、「月下推敲」という四字熟語の方が、由来を連想させる言い回しとなっています。
推敲とよく似た意味の校正の意味の違いは?
推敲とよく似た意味の校正の意味の違い①推敲は文章の練り直しも含めた校正

推敲とよく似た意味の校正の意味の違いの1つ目ですが、推敲は文章の練り直しも含めた校正を意味します。推敲という言葉を使う際には、文章の日本語表現が適したものであるか、また誤字脱字があるかどうかというような部分だけでなく、文章の内容についてももっと改善できないかといった観点も含めた修正を意味します。
そのため、たとえ文章的に問題がない場合でも推敲をする場合には能動態を受動態にした方が分かりやすいといったことや、主語を入れ替えて視点を変えた表現にするなど、幅広く修正をする形になるのです。推敲をすれば、書き直すごとに文章は洗練されていくものなのです。
推敲とよく似た意味の校正の意味の違い②「校正する」は主に誤字脱字の修正

推敲とよく似た意味の校正の意味の違いの2つ目ですが、「校正する」は主に誤字脱字の修正を表します。文章を修正する場合には「推敲する」という場合と「校正する」という場合に分かれます。「校正する」という表現については、主に誤字脱字の修正や日本語文法の誤りを修正するにとどまる表現です。
「推敲する」という言葉を使う場合には、文章表現自体も吟味されることになりますが、「校正する」という表現については文章の誤りのみを修正するといった形になり、2つの表現は似ているようですが、それぞれ違った修正のニュアンスを表す言葉になります。意味を混同しやすい表現ですので、注意して使い分けましょう。
推敲を英語に置き換えるならどんな言葉になる?
推敲の英語表現①improve

推敲の英語表現の1つ目は「improve」です。「improve」は改善するという意味の英単語であり、推敲という言葉を英語表現にするには文章として表現する必要があります。「improve」を使った文章が推敲を表す英語表現にはなりますが、「improve」自体が推敲と全く同じ意味にはなりません。
I improve the writing of the novel he wrote.(私は彼が書いた小説の推敲をします)
推敲の英語表現②rewrite

推敲の英語表現の2つ目は「rewrite」です。rewriteは書き直すという意味の英語表現であり、「リライト」といった形でカタカナで使われることも多い表現です。一般的に原稿を推敲する場合や、出版業界における推敲については「improve」よりも「rewrite」という英語表現がよく使われます。
I rewrite the novel he wrote.(私は彼が書いた小説の推敲をします)
推敲の類語と対義語はある?
推敲の類語①校閲

推敲の類語の1つ目は「校閲」です。「校閲」という類語は、文章の誤りや不適切な表現の有無を調べて、文章を修正することを意味しています。推敲との大きな違いとしては、校閲という言葉を使う時の方が、文章内の内容や表現の適切性においてより専門的な内容について吟味される点です。
例えば推敲という言葉は自分で書いた原稿を直す場合に使うこともありますが、校閲という言葉はそのような使い方をしませんし、また校閲を行う人もその文章内容に関する専門性の高い人が行うものになっています。校閲という類語表現も覚えておきつつ、推敲と使い分けられるようにしましょう。
推敲の類語②添削
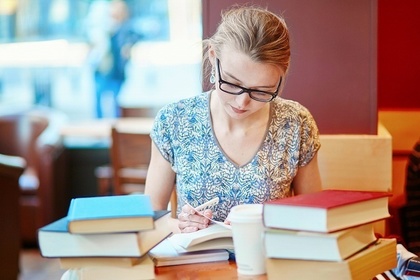
推敲の類語の2つ目は「添削」です。添削という類語表現は、文章や答案に対して何かを付け足したり削ったりして、より良くすることを示しています。文章だけでなく答案に対しても使うことのできる類語表現であり、校閲に比べると内容の吟味の要素が薄い言い回しになっています。
推敲の対義語はないので「文章の改悪」など状況により表現する
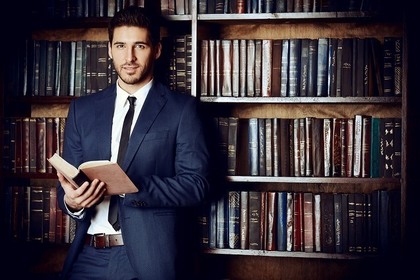
推敲の対義語はないので「文章の改悪」など状況により表現します。推敲のように、対義語がない日本語表現は少なくありません。推敲も対義語表現がない日本語の一つであり、その対義語の意味を言い表したい場合には、その都度状況に合った表現を使っていきます。
例えば「せっかくいい作品に仕上がったのに、彼の手入れが入ったことで文章の改悪となった。せっかくの佳作が台無しだ」といった形で使います。この表現は文章が悪い方に加筆および修正されてしまったことを示しています。中々ない状況ではありますが、対義語を表したい場合にはこのような言い方をします。
推敲という言葉を語源や意味からしっかり理解し使いこなそう!
推敲という言葉の意味や故事成語に由来する語源をしっかり理解しながら使うことで、説得力のある言い回しができるようになります。また推敲という言葉は様々な業界において原稿や文章の手直しが必要な場合に使われる表現です。ここでは類語や英語表現も含めてその使い方を紹介してきました。
推敲のような表現が自然に使えるようになると、仕事における相手からの信頼を集めやすくなりますし、またその意味や語源を理解して仕事に臨むと、何かの拍子に語源を雑学として披露するような状況になった時に、相手から一目置かれることでしょう。ここで紹介した推敲の知識を、ビジネス等の場面で活用してください!
商品やサービスを紹介する記事の内容は、必ずしもそれらの効能・効果を保証するものではございません。
商品やサービスのご購入・ご利用に関して、当メディア運営者は一切の責任を負いません。
![chokotty[ちょこってぃ]](https://cktt.jp/assets/common/cktt_logo_PC_2-40c5a35e8da64f225f3dcdf1b548a3f3373f85eeab336668a1c00fe9a8ab42c8.png)










