朱書きとは?封筒の位置やボールペンでの書き方・訂正方法も
朱書きとは封筒などに手書きや印刷されている「○○書在中」といった部分のこと。これ以外にも年賀・速達・書留といったものも朱書きです。もし自分が受け取った場合、さらに自分がボールペン等で朱書きする場合、どうすればよいのでしょうか?朱書きやの書き方・朱字による訂正のルールについて知っておきましょう。
※商品PRを含む記事です。当メディアはAmazonアソシエイト、楽天アフィリエイトを始めとした各種アフィリエイトプログラムに参加しています。当サービスの記事で紹介している商品を購入すると、売上の一部が弊社に還元されます。
朱書きとは?読み方や起源・役割も
「朱書き」の読み方・種類について

朱書きの読み方は「しゅがき」です。封書の宛名面に赤い囲みの四角で書かれてある部分のことです。私たちが普段からよく目にするものとしては、納品書在中・請求書在中・親展(しんてん)といったものがあります。自分で書かずとも専用のスタンプなどもありますよね。
また年賀はがきのようにすでに「年賀」と印刷されているものや、速達の際に押印される封書の上部の「速達」、さらに「簡易書留」「特定記録郵便」も朱書きにあたります。
そもそも朱書きをするのはなぜでしょうか?それは封筒の中を開けなくても、中にどういった書類が入っているのか「はっきり目立つように」伝えるためです。どういった書類が入っているのか、封書を受け取った人がわかるように朱字で朱書きするのです。
朱書きは朱字(朱色の字)である必要はない

朱書きの朱は朱色(しゅいろ)です。現在はボールペンを使いますが、昔は筆と墨汁を使って書類の作成をし、目立たせたい部分は朱色の液を使用していました。毛筆を習っている人ならすぐにわかると思いますが、毛筆の先生が字の訂正をする場合には墨汁ではなく朱色の液(朱墨液)で訂正します。
つまり訂正部分を目立たせるために朱色の液を使用していたことが、朱書きの起源と考えられています。ただし現代においては筆ではなくボールペンで書類を作成することから、利便性を考えて赤のボールペンが利用されているのです。朱書きは朱字(朱色の字)である必要はありません。
朱書きのポイント
朱書きに関して押さえておきたいポイント:親展・請求書在中などの場合
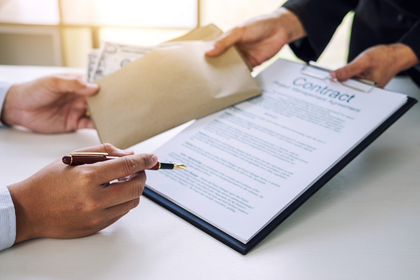
まず最初に朱書きの封書を受け取った時のポイントについてです。もし「親展」と記載されていたら、封書の宛名人以外の人は開封できません。開封せずにそのまま宛名人に渡すようにします。宛名の人から送り主を特定されて、事前に開封を許可されている場合はこの限りではありません。
会社などにおいて請求書在中・納品書在中といった朱書きの封筒が送られてきたら、基本的に開封せずに請求書や納品書を担当している人に渡します。履歴書在中であれば採用・人事担当者といったようにです。わざわざ開封せずに中身がわかるので、そのまま担当の人に渡せるのが朱書きのメリットと言えるでしょう。
特に郵便物が毎日大量に届くような会社では、担当の部署に郵便を振り分けるのが大変なところもあります。わざわざ開封して中身を確認するよりも、朱書きであらかじめどのような書類が入っているのかを明確にしておけば、相手にも負担を掛けずに担当者にスムーズに渡っていきます。
名前の朱書きがタブーな理由とは

朱書きで一番のタブーは「人の名前を朱書きしないこと」です。人の名前を赤い文字で記載してはいけない理由としては次のような理由があります。
- ・(存命中の)墓石の名入れが赤い文字だから
- ・赤い文字で名前を書くとその名前の人が早死にするという迷信
- ・絶縁状や果たし状(決闘の申込)の宛名が朱色で書かれていた
- ・罪人の名前が朱色で書かれていたため
人の名前の朱書きNGの理由
朱書きNGの理由はたくさんありますが、具体的な理由を知らなくても「何となく縁起が悪い」ということで人の名前を赤で書くのを嫌う傾向が強いようです。さらに「あなたのことが嫌い」というケースでも赤で名前を書く習慣があるので要注意です。
名前の朱書きは基本的にしないこと

自分の名前を赤い文字で記載されていても、何とも思わない人もいるかもしれません。自分は迷信だと感じていても、赤い文字で自分の名前を書かれた人の多くは不快に感じるというケースがあることも決して忘れてはいけません。
中でも年上の人や礼儀を重んずる人なら、自分の名前を朱書きされることを快く思わないでしょう。そういった背景も理解して、特にビジネスにおいては人の名前を朱書きするのは避けるようにしましょう。
名前の朱書きにはこんな例外もある

しかしながら、地方の風習によっては名前を朱書きするケースもあります。有名なのは三重県では慶事の内祝いののしに記載する名前は朱書きです。地方の風習やならわしによっては名前の朱書きがOKなケースもあります。
このように非常にまれなケースではありますが、日本のごく一部の地域によっては、名前を朱書きすることが望ましいケースもあるようです。名前を朱書きする場合には、事前によくリサーチしておきましょう。
朱書きの書き方や例も
封筒の朱書きの位置と書き方

では実際に自分が朱書きをする時はどうすればいいのでしょうか?朱書きの書き方は請求書・納品書であれば、封筒の宛名面に請求書在中・納品書在中といったように赤のボールペンで朱書きします(朱字)。宛名人だけに開封して欲しい場合には「親展」と記載します。
朱書きをしていない場合には、中の書面がどういったものなのかわからないばかりか、企業名で差し出している場合にはダイレクトメールと勘違いされて破棄されてしまうこともあります。大切な書類はもちろん、請求書などの場合には極力朱書きする方が望ましいでしょう。
朱書きをする位置ですが、縦型の封筒であれば左下に記載します。また横長の封筒であれば右下に記載するようにします。赤のボールペンで記載する時には請求書在中といった朱字部分を必ず四角で囲むようにします。フリーハンドで四角の囲みを書くよりも、定規などを使って囲みを書くようにすると見栄えも美しくなります。
封筒の朱書きに使うボールペンについて

朱書きに使うペンですが、文字が読みにくい・つぶれることのないよう、にじみの少ないペンを利用するようにしましょう。中身を入れてから朱書きするよりも、中身の入っていない状態で朱書きした方が無難です。雨にぬれても消えないように油性のボールペンを利用するといいでしょう。
熱や摩擦で消えてしまう特殊なインクが使われているボールペンなどを使用するのは避けましょう。朱書きだけではなく宛名書きや大切な書類に使うのもNGです。
ただし普段から請求書や納品書、親展扱いにして封書を出す機会が多いような場合には、専用のスタンプなどを用意している場合があります。会社でそういった封書を出すことがあるのなら、そういったスタンプがないかどうか確認しておくとよいでしょう。朱書きを手書きするよりも手間が省けます。
朱書きのスタンプが水色の理由

市販されている請求書在中といったスタンプの中には、すでにセットされているインクが赤ではなく水色のものがあります。「朱書きなのにどうして水色なの?」と思うかもしれませんが、本来朱書きは「目立たせる」ことが目的なので、水色でも問題ないのです。
さらに、請求書はお金に関する言葉です。この「請求書在中」という文字を朱字にすることは、「赤字」つまり経営状況が思わしくないという意味の赤字になってしまうという解釈をする人も多いようです。
そのため請求書以外にもお金にかかわる書面(納品書など)を同封している場合、「納品書在中」といった文言も朱字ではなく青(水色)で記載することが一般的になっています。お金に関する書面を封筒で送る場合には青(水色)で朱書き、あるいはすでにインクが装着されている市販のスタンプを利用するといいかもしれません。
郵便で注意しておきたい朱書き

また朱書きで注意しておきたいのは年賀状です。年賀状にはすでに「年賀」と印刷された年賀はがきを利用する人も多いので気が付かない人も少なくないかもしれません。しかし、年賀はがき以外のはがきで年賀状を作成した場合には忘れずに「年賀」の朱書きを忘れないようにしましょう。
もし「年賀」という朱書きをしないままで投函してしまった場合には、1月1日よりも前、つまり年内に相手に年賀上が届いてしまうことがあります。これは年賀という朱書きがないために普通郵便として扱われてしまうためです。年賀はがき以外のはがきを利用して年賀状を作成する時には十分注意しましょう。
郵便の種類によっては速達・簡易書留・特定記録といった朱書きが必要になります。ただし書留や特定記録は「確かに郵送しました」という証拠が必要な時に利用するもので、郵便局の窓口を経由して郵送するものです。朱書きを忘れたとしても、郵便局側で押印してくれます。
朱書きの訂正方法
朱書きの訂正方法

朱書きの書き方として、封筒やはがきの宛名面に赤のボールペンで記載するということをお伝えしていますが、封筒の中にどのような書類が入っているかを教えるだけではありません。
朱書きで文章などを訂正するケースもあります。文章を朱書きで訂正する場合には、訂正したい箇所を赤の二重線を引き、その上に訂正印を押します。修正箇所を見やすくするためにも二重線は定規を使って丁寧に引きましょう。そして正しい内容の文字や文章を近くに記載するようにします。
訂正印とは一般の認印よりも一回り小さい印鑑のことです。訂正印がなければ認印でもOKですが、訂正箇所や修正した文字などをハッキリ・スッキリ見せるためにも小さな印面の訂正印があると便利です。
二重線を引いて朱書きの訂正をする書き方「見え消し」について

二重線を引いて朱書きの訂正をする書き方を「見え消し」といいます。修正液を使った文書の訂正と違って、訂正前にどのような内容が記載されていたのかがわかります。
文書などの修正を行う際に黒いボールペンで二重線を引いているケースがありますが、これは正しくは「その部分を削除する」ことになってしまうので注意しましょう。会社などによっては二重線では訂正前の内容が確認しづらいなどの理由から一本線に統一しているところもあるようです。
訂正・修正を行う場合には会社によってルールを設けている場合がありますので、会社においては会社のルールに従うようにしましょう。
朱書きの訂正の例外について

朱書きの訂正には例外もあります。同封されている返信用封筒を利用する場合、その返信用封筒の宛名の下に「行」と書かれていることがあります。この「行」は必ず黒の二重線で消して、余白に「様(あるいは御中)」と書き入れるようにします。
返信用封筒の宛名の部分を黒の二重線で訂正するのは、先ほどもお伝えしたように名前の部分に赤い文字を使うことを嫌う人が多いことに由来しています。朱書きの見せ消しで、人の名前に関わる部分がある場合には、赤ではなく黒のボールペンを利用するよう注意しましょう。
金額の訂正をする場合の注意

文章中の金額などを訂正する場合には注意が必要です。間違えた数字の部分だけを朱書きするのではなく、金額の額面全体を修正するようにします。
例えば30,000と記載しなければいけないところを、50,000と誤って記載してしまったとしましょう。この場合先頭の3だけに二重線をして訂正するのではなく、50,000という部分全体に二重線を引きます。そして訂正印を押し、余白にわかりやすく正しい「30,000」という朱字を記載するようにします。
朱書きは「相手のために」するものだということを忘れずに

朱書きがどういったものなのか?さらにどういったシーンで必要なのか、さらに基本的な書き方ついて詳しくお伝えしました。朱書きの書き方については、会社によって細かいルールなどもありますが、いずれにしても朱書きは書類が渡っていく「相手のために」するものです。
自分の都合ではなく相手の利便性などを考えて朱書きを行うようにしましょう。社会人の常識・マナーとして「朱書き」の書き方の基本を知っておけば、会社以外のどのようなシーンでも応用がききます。
ただし朱書きの書き方・ルールは会社や地域などによっては特殊な例もあるので、事前に独自ルールがあるのかどうか、しっかり確認しておくことも大切です。
商品やサービスを紹介する記事の内容は、必ずしもそれらの効能・効果を保証するものではございません。
商品やサービスのご購入・ご利用に関して、当メディア運営者は一切の責任を負いません。
![chokotty[ちょこってぃ]](https://cktt.jp/assets/common/cktt_logo_PC_2-40c5a35e8da64f225f3dcdf1b548a3f3373f85eeab336668a1c00fe9a8ab42c8.png)










